(7)曼荼羅の外へ
曼荼羅の内部での長い時間が、ようやく終わりを告げた。堂の扉が静かに軋み、外の光が差し込んだ瞬間、デカルトは目を細めた。淡い霧を含んだ山の空気が、頬を撫でて通り過ぎていく。その感触は、まるで長い夢の外に戻ってきたことを告げる手触りのようだった。
彼は思わず深呼吸をした。澄んだ風が肺に満ち、胸の奥に広がっていく。堂内で幾重にも重なった色と音の渦に包まれていた後の空気は、まるで別世界の息吹であった。
それは「外」ではなく、「新しい内」――心の奥深くまで通う風のように感じられた。
石段を降りると、朝露を帯びた苔が金緑に光っていた。足元の岩の隙間を、細い流れが音もなく走っている。
その水は透明で、岩肌を撫でながら、小さな葉を抱き、やがて渦をつくっては静かにほどけていった。
デカルトは立ち止まり、その繊細な動きを見つめた。
──曼荼羅の図に似ている。
一滴の水が孤立して存在することはない。それは流れ全体の一部として、絶えず変化しながら、他の滴と結び合い、また離れ、再び交わる。曼荼羅で見た縁起の網が、いまここに、風と光と水の中で息づいていた。
「空海……私は外に出ても、曼荼羅を見ている気がします」 デカルトの声には、静かな驚きと敬虔な響きが混じっていた。「川の流れも、鳥の声も、木々のざわめきも──すべてが曼荼羅の一部に見えるのです」
空海は頷き、遠くの山稜に目を向けた。霧の切れ間から射す光が、彼の頬に淡く映えている。
「曼荼羅は堂の壁に描かれた図ではありません」
空海の声は柔らかく、それでいてどこか透き通っていた。
「あなたが目を開き、耳を澄ませ、心を澄ませるなら、世界そのものが曼荼羅となる。 色も音も匂いも──すべてが縁起の網の中で互いに響き合っているのです」
その言葉に呼応するように、一羽の鳥が枝から飛び立った。羽ばたきの音が風を裂き、青空へと吸い込まれていく。その軌跡は曼荼羅の一線のように、空に淡く刻まれた。
やがて道端に、一輪の白い花が咲いているのを見つけた。 朝露を宿した花弁は、日の光を受けて微かに虹色を帯び、静かに揺れていた。 デカルトは足を止め、その小さな存在に深い敬意を覚えた。 ──曼荼羅の中心で見た光と同じだ。 花の中に、宇宙の全体が凝縮されている。 それは単なる美しさではなく、世界をつなぐ「縁」の象徴であった。
「私はこれまで、世界を“外側”から観察してきました」 デカルトはゆっくりと語った。「理性という窓から、対象を切り取り、分析し、理解しようとしていた。 しかし……今は違います。 私はこの世界の中で息をし、歩き、風に触れています。 私自身もまた、この曼荼羅の網に結ばれているのです」
空海はその言葉を聞きながら、微笑んだ。「それこそが“曼荼羅の外へ出る”ということです」 彼は山の風を受けながら続けた。
「曼荼羅は閉ざされた図ではありません。あなたの眼差しが変わるとき、その曼荼羅もまた変わる。世界をどう見るか──その態度が曼荼羅を形づくるのです」
風が吹き抜け、木々の葉がざわめいた。 その音は、堂内で聞いた法螺の響きにも、磬の余韻にも似ていた。 デカルトは目を閉じ、ざわめきを曼荼羅の旋律として聴いた。 音はすぐに沈黙に還り、沈黙はまた音を生む。 あの堂で体験した循環が、山の自然の中にも生きていた。
彼は歩みを止め、深く息を吐いた。
──曼荼羅は歩むごとに開かれる。 ──中心は定まらず、しかしすべてが中心である。 ──私はその網の中に結ばれている。
その確信は、彼の胸に静かな力を与えた。理性は否定されず、感覚も排除されない。どちらも曼荼羅の全体に迎え入れられている。かつて孤独な探求の中で抱えた不安は、いまや広大な網の一節として抱かれていた。
デカルトの心には、ふとある記憶がよぎった。遠いフランスの書斎、冷たい夜気の中でひとり思索していた日々。白い紙の上で理性を研ぎ澄まし、世界の構造を描こうとしたあの時間。
だが、いま目の前に広がる自然の中で、彼はその同じ構造を感じていた。思索ではなく、呼吸とともに。
それは「理解」ではなく、「共鳴」と呼ぶべき体験だった。
やがて霧が薄れ、谷を流れる川が朝日に照らされて輝いた。水面に散る光が、まるで曼荼羅の中心から放たれる光線のように山肌を染めていく。 デカルトはその光景を見つめ、言葉を紡いだ。
「空海……私は、ここに“世界の座標”を見ています」 彼の声には、もう迷いがなかった。
「理性と感覚、沈黙と音、中心と周縁──それらは対立ではなく、一つの曼荼羅に収められている。私はもはや、外側から観察する者ではありません。この世界と共に歩む一つの節として、次の道へ進みます」
空海は深く頷いた。 その頷きは、言葉を超えた祝福のようだった。
二人は並んで山道を歩き出した。 鳥の声が空へ響き、川のせせらぎが寄り添い、風が背を押した。 足元には柔らかな光が揺れ、木々の影が曼荼羅の模様のように地を覆っている。
曼荼羅を越えた歩みは、やがて「世界の座標」へと至るだろう。 その道は終わりではなく、世界が自らを語り始める新たな始まりであった。 彼らの背を、朝の光が静かに照らしていた。
山の稜線の向こうに、雲がゆっくりと流れていた。 その形は次々と変わり、やがてどの輪郭も溶け合って消えていく。 デカルトは足を止め、空を仰いだ。
──世界は、もはや固定された地図ではない。 それは生きて動く曼荼羅であり、見る者の心とともに形を変えてゆく。
そのとき、遠くから鐘の音が響いた。 谷を渡り、風に乗って届くその音は、言葉ではなく、ただ“呼びかけ”そのもののようであった。 空海は静かに立ち止まり、目を閉じた。
「デカルトよ。これから見るものは、曼荼羅の“外”ではなく、“内と外が溶けあった座標”です。理性と霊性、思索と祈り、そのすべてが交わる場──それが“世界の座標”なのです」
デカルトは頷いた。 胸の奥で、ひとつの言葉が静かに芽吹いていた。
それは、彼が長く探し求めてきた「思考の中心」ではなく、いま初めて見つけた「存在の共鳴点」だった。
そして二人は再び歩き出した。 光の道が山の奥へと続いていた。
その先で、世界の全ての線が交わる座標が、彼らを待っていた。
つづく…



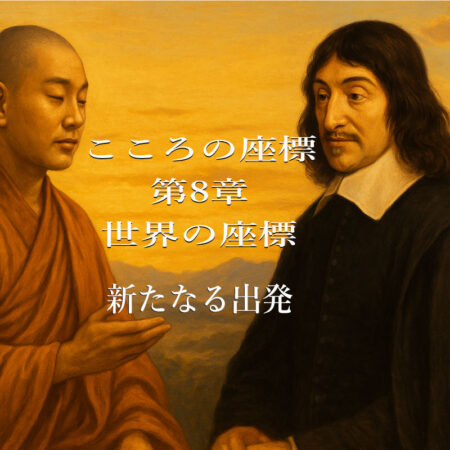

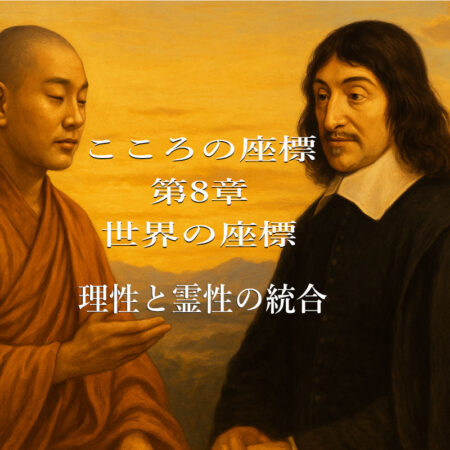
























コメントを残す