(3)老婆との邂逅
村を離れて半日ほど歩いただろうか。
空は曇り、陽はほとんど地上に届かず、風景は薄墨を流したような色合いに沈んでいた。
道と呼べるものはなく、乾いた土の上に獣の足跡のような凹みが続いているだけだった。
その道の端に、人影が見えた。膝を抱えて座り込む老婆である。
背は丸まり、髪は乱れて白く、衣はほつれていた。
両手で小さな壺を抱えていたが、中は空らしく、風が吹くたびに軽く音を立てていた。
デカルトが近づくと、老婆は顔を上げ、乾いた声で言った。
「……水……を……」
その一言は、かすれながらもはっきりとした響きを持っていた。
デカルトは水袋を探り、残り少ない水を壺に注いで差し出した。
老婆は両手でそれを受け取り、口を濡らした。喉が細く鳴り、やがて深い吐息が漏れた。
老婆は目を細め、しばらく黙っていたが、やがて低く問いかけた。
「旅の方……あなたは、どこへ行くのです」
デカルトは答えに詰まった。自分自身、まだ「どこへ行くのか」を明確に掴んではいなかった。
ただ、問いに導かれるようにして言葉を探した。
「……私は、私自身を確かめに行くのです」
老婆は小さく頷いた。その頷きは理解というより、ただ存在を肯定する仕草に見えた。
やがて彼女はぽつりと語り出した。
「このあたりは、かつては豊かな村でした。畑には麦が実り、祭りの日には歌と太鼓の音が響いてた……。
けれど、干ばつが続き、病が広がり、戦が人を奪っていった。息子も……戦に行って、帰ってはきませんでした」
その言葉は乾いた風と共に流れ、荒野に溶けた。
老婆の瞳は、遠い記憶を映すように揺れていた。
デカルトは静かに問うた。
「なぜ、人は苦しまねばならないのでしょうか。理性があれば、戦も飢えも避けられるはずだ。人が協力し、知恵を分かち合えば――」
老婆はかすかな笑みを浮かべた。その笑みは嘲りではなく、ただ静かな疲労の色を帯びていた。
「人は、生きているから苦しむのです。生きている限り、飢えも争いも、避けられはしない……」
その答えは理屈ではなかった。だがデカルトには、その素朴な言葉が理性よりも重く響いた。
沈黙が二人を包んだ。遠くで風が草を揺らし、壺が空虚な音を立てた。
デカルトは胸の奥に重い痛みを感じた。理性は答えを与えようとするが、老婆の言葉の前では無力だった。
論理は未来を描くが、彼女の声は今を生きるための声だった。
やがて老婆は立ち上がり、杖をついて歩き出した。
背中は小さく、影は霧に溶けていった。
デカルトはその姿を見送りながら、心の中で呟いた。
「理性は未来を指し示す。しかし、いまを生きる声を抱きしめることができるのは、理性ではないのかもしれない……」
彼は再び歩き出した。道は果てしなく続き、霧はまだ晴れなかった。
だが老婆の言葉は、彼の胸に沈殿し、思索の石として重みを増していた。
つづく…

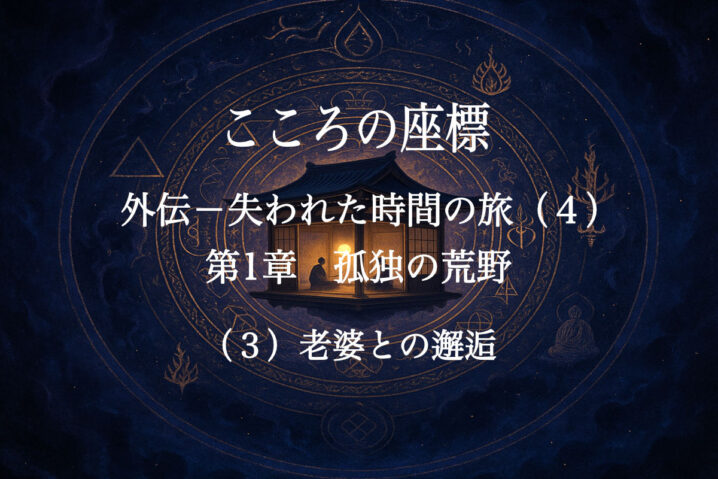






















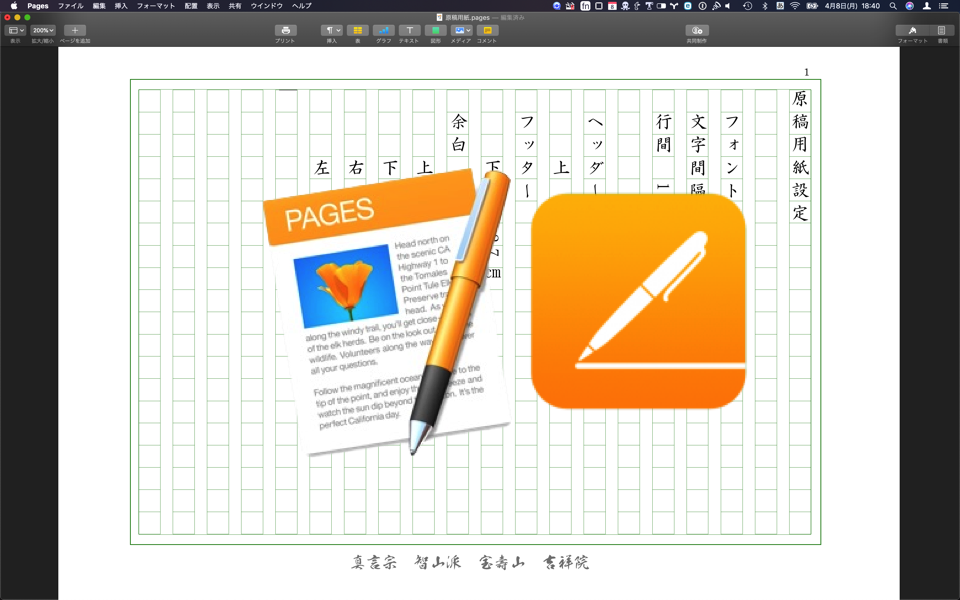

コメントを残す