(6)中心なき中心
曼荼羅の迷宮を歩むうち、デカルトの視線は次第に一点に吸い寄せられていった。
堂の内部は単なる建築ではなく、呼吸する宇宙であった。光は線ではなく粒となって漂い、時に花弁のように旋回し、時に炎の舌のように立ち上る。
壁も天井も床も境を失い、色彩は液体のようにたゆたい、触れると指先に温度を残した。
朱は体温を上げ、群青は額の熱を奪い、黄金は胸腔の奥に低い鐘の音を共鳴させ、翡翠は草いきれの記憶を運ぶ。
沈香と塗りの匂いは形を帯び、耳には聞こえないはずの梵音が、脈拍と同じ速さで押し寄せては退いた。
それほどの渦中にあっても、彼の心はなお「中心」を求めた。
これまでの哲学は拠り所を探す営為だった。すべてを疑い、解体し尽くした末に残った「我思う、ゆえに我あり」。
それは荒天の海から船を護る錨であり、霧の高台に掲げる標識であった。
だが曼荼羅の只中では、その錨が砂に沈む。結び目がほどけ、綱がたわみ、確かだと信じた重みが指の間から零れていく。
中心は見える。けれど近づくほど輪郭が揺らぎ、遠ざかるほど逆に際立つ。まるでこちらの視線が中心を生成し、次の瞬間には自ら消し去っているかのようだ。
見ようとすれば逃げ、見ないと決めれば至るところでこちらを見返す。論証の線はそこへ届かず、地図に記された方位は、近づくたびに回転する羅針盤の針となる。
「空海……私は“中心”を確かめたい。中心のない秩序を、私はまだ信じきれない」
声は堂に吸い込まれ、幾重もの反響となって返った。己の言葉が自分を責めるように聞こえ、胸の奥で、長年組み上げた論理の梁がきしむ音がした。一本でも柱が倒れれば塔は崩れる――その予感が彼の背筋を冷たくした。
空海は近づき、淡い微笑とともに言葉を継いだ。
「中心はあります。しかしそれは“石”のように動かぬものではなく、“器”のように空であり続けるものです」
その瞬間、曼荼羅が大きく震えた。
中央に坐す尊像が光を放ち、一つが二つに、二つが四つに、雪片の増殖のように分かれていく。
だがそれは争いではない。分裂のたび、像は互いに音叉のように共鳴し、新たな和声を生み出した。複数の中心が同時に「ここだ」と名乗りながら、互いを否定せず、むしろ支え合っていた。
デカルトは後ずさりしかけたが、足元は沈まず、柔らかく彼を受けとめた。石ではない、しかし沼でもない。たわみながら戻る弾力があり、彼の重さを測り、ちょうどよい深さで安定させる掌のようだった。
──中心は一つではない。
──中心は至るところに現れ、至るところで消える。
理解は遅れ、直観が先に届いた。混乱が胸を満たすのに、どこかで安堵が芽吹いている。
唯一の石を見失ったはずなのに、呼吸は深く、肩の力は抜けていた。硬い地面にしがみつく必要がないと身体が知ってしまったのだ。
「器は満ちては空き、空いては満ちます」
空海の声は、堂全体の材に吸い込まれて広がった。
「中心とは固定された点ではなく、受け渡しの場です。空であるがゆえに縁を迎え入れ、また手放すことができる」
デカルトは、その言葉に触れたとき、幼い日の井戸が甦った。木枠に腹を預け、水面を覗く。顔はたちまち歪み、伸び、波紋とともに崩れ、やがて澄んだ像に戻る。
水は空だから映し、映すからこそ消せる。もし井戸が石で満ちていたら、そこに像はなく、ただ重みだけがあっただろう。
空とは拒絶ではなく、受容の形式なのだ。
さらに、初等学院の回廊で読んだ幾何学の図版を思い出す。点は位置を持つが大きさを持たない。線は無数の点の連なりであり、面は線の広がりであり、立体は面の積み重なりだ。
では「中心」とは何か。図形の内部に与えられた、すべてから等距離の一点。
しかし曼荼羅の内部では、等距離の条件そのものが呼吸のたびに更新され、計測の基準が生まれては消え、消えては生まれる。
――基準は外に固定されていない。基準は関係の網の振る舞いとして現れる。
彼は膝を折り、冷たさと温かさが交互に伝わる床に座した。目を閉じる。内奥にも曼荼羅が広がる。
思考の中心を凝視しようとすると、それは蜃気楼のように遠のき、代わりに周縁のざわめきが整列して、緩やかな円環の気配だけが残る。
耳を澄ませば、遠近の区別なく小さな鐘が鳴り、その余韻が網の目を渡っては戻ってくる。自我という点は、独立した核ではなく、張り巡らされた縁の節に過ぎないと、胸の内が了解していく。
──中心はどこにもなく、同時にすべてにある。
その一句が、長い冬の霧の中で俄かに日が差すように、彼の内側を明るくした。論理は矛盾を恐れる。矛盾を排除した地平にこそ、真理の城は建つと信じてきた。
しかし曼荼羅は矛盾を抱えたまま秩序を保ち、むしろ矛盾同士の張力こそが全体を立たしめている。中心が定まらないから崩れるのではない。定まらないからこそ、全体が互いに支え合っている。
思索の道程が走馬灯のように巡った。薄暗い部屋で、夜更けの燭の火を相手に格闘した。
師の叱責と友との議論、書物の余白に残した震える書き込み。孤独を単数形で語っていた時期が、実は複数の縁に支えられた合唱であったことに、いまさらながら気づく。
私の「我」は、私だけの所有ではなかったのだ。
中央から発した光は、波紋となって幾重にも外周へ広がり、反射してまた内へ戻る。朱は群青に染まり、群青は金へ溶け、金は若葉のような緑に交わる。色は互いを消さず、互いの成分を少しずつ借り受け、より深い色相を生む。生成と消滅は対立ではなく、往還の両端であると、目ではなく皮膚が学び取る。
彼の鼓動は、その往還に重なった。石に凭れる安心ではなく、水に抱かれる安堵。線の確かさではなく、波の確かさ。怖れは残る。だが怖れだけが真実ではないと、胸の奥で小さな灯が続いている。
若き日の海辺が浮かぶ。オランダの風。潮の匂い。波は形をとどめないのに、そこには頑固な周期があり、間違いなく帰ってくる拍がある。
彼はその拍に呼吸を合わせ、やがて自分の足裏が砂に沈み、また持ち上がるたび、世界が自分を突き放すのではなく、押し返し過ぎない力で受けていることを知った。
曼荼羅の呼吸は、あの海の律動に他ならない。
「空海……私はいま、“我思う”を超えているのかもしれません」
空海はかすかに首を振った。
「超えるのではなく、包むのです。理性は空に否定されるのではなく、空に抱かれる。あなたの理性は、ここで役目を終えるのではなく、居場所を変えるだけです。硬い核から、たわむ器へ。拒絶から、受け渡しへ」
言葉は説教の調子を避け、ただ事実を述べるように彼の胸へ落ちた。
彼は長く固着していた筋肉が緩むのを感じる。眉間の皺がほどけ、歯の食いしばりが外れ、舌の根が喉の奥で位置を変えた。身体はいつも理性より早く知っている。
中心が「置くもの」から「起こるもの」へ変わったとき、呼吸は勝手に深くなる。
堂内は静寂に満たされた。だがその静寂は無音ではなく、数え切れない微細な活動の総和としての静かさであった。
灯の小さな揺れ、衣のきしみ、遠くの木組みが湿気に応じて鳴らす微音。それらが互いの邪魔をせず、同じ呼吸の中で収まっている。
中心なき中心――その名にふさわしい気配が、堂の隅々にまで行き渡る。
デカルトは合掌し、深く一礼した。砕かれたのではない。置き換わったのだ。塔の頂に掲げた旗印は降ろされ、代わりに器が据えられた。器は空であるがゆえに、これから訪れる未知の対話と出来事を、過不足なく受け入れるだろう。
彼は静かに顔を上げ、遠くと内奥の双方を見た。両者の間に境はなかった。
堂の外で、風が杉を渡る音がした。その音は、さきほど聞いた海鳴りにも、学舎の回廊の足音にも、井戸の水面の波にも似ていた。
世界は別々の出来事を別々の場所で起こしながら、同じ拍で呼吸している。彼はその拍に歩幅を合わせ、立ち上がる。足元はやはり柔らかく、しかし確かだった。器の底は見えないが、必要なだけの深さがある。
空海は彼の横に並び、短く言った。
「さぁ、行きましょう」
その言葉は指示ではなく、招きであった。デカルトは頷く。中心を探す旅は終わらない。
だが、中心を「固定された一点」だと決めつける旅は、ここで終わった。
これからは、起こる中心、受け渡される中心、関係のうちに生まれる中心――その数だけの中心とともに歩くのだ。
二人が歩みを進めると、背後の曼荼羅はゆっくりと色を落とした。しかし消えはしなかった。
彼の内に、器としての空が確かに残っていたからだ。
彼はもう、渦に呑み込まれることを恐れてはいなかった。渦そのものが、器のかたちであると知ったのだから。
つづく…

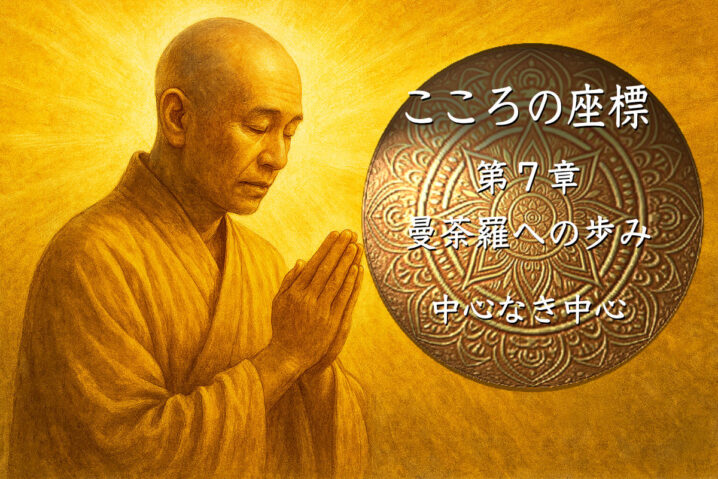


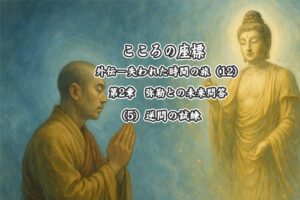
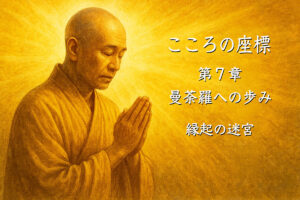

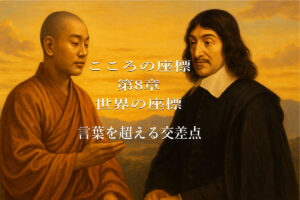
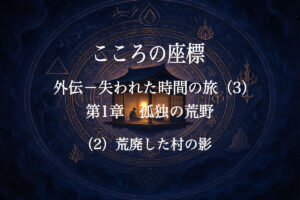

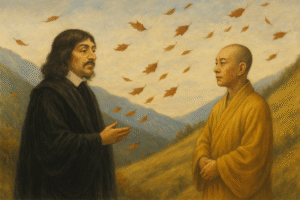
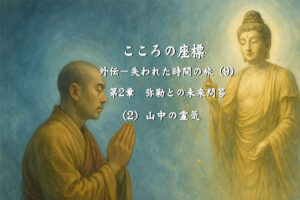
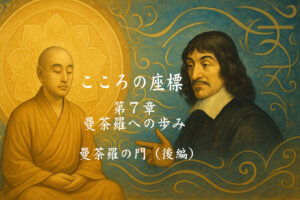
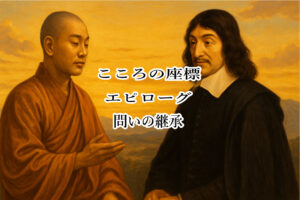










コメントを残す