(2)荒廃した村の影
霧の幕を抜けると、地形がわずかにひらけた。かつて畑であったと思われる土地が広がっている。しかし土はひび割れ、草は茶色に枯れ、ところどころに残る石垣だけが耕作の名残を示していた。
デカルトは歩を止めた。前方に小さな屋根が見える。低く傾いた家が数軒、寄り添うように建っている。煙突からは細い煙が上がっていたが、焚かれているのは薪ではなく、湿った藁か枯れ枝のようで、煙は重たく鼻を刺した。
村に近づくにつれて、人々の姿が見えてきた。子どもたちが裸足で立ち尽くし、母親たちが疲れきった眼で空を仰いでいる。
男たちは腰を落として座り込み、手には何の道具も持っていない。耕す畑も、収穫する作物もないことを示していた。
一人の母親がデカルトに気づき、慌ただしく駆け寄ってきた。頬はこけ、唇は乾いてひび割れている。その腕に抱かれた幼子は、ほとんど泣く力さえ残っていないようだった。
「み……水、食べ物……を……」
母親は絞り出すように言葉を吐いた。
デカルトには完全には聞き取れなかったが、その必死さで意味は伝わった。デカルトは外套の内側を探った。指先に触れたのは、出発のときに残していた乾いたパンの欠片だけだった。
それを差し出すと、母親は両手で受け取り、すぐに子どもの口に押し込んだ。子どもは弱々しく咀嚼し、喉を動かした。
母親は涙を浮かべて何度も頭を下げた。その姿を見ながら、デカルトは胸の奥に重たいものを感じた。
「人は、理性によって飢えを避ける術を見出せるはずだ。
土地を耕し、収穫を分け合い、備蓄を管理すれば……」
彼は母親に向けて言葉を発した。だがその声は、虚空に投げられたように消えていった。母親の瞳にはただ「今を凌ぐ糧」しか映っていなかった。
理性が描く未来の仕組みは、空腹の現実の前では意味を持たなかった。
母親は震える手で子を抱きしめ、声にならない嗚咽を洩らした。
デカルトはそれ以上何も言えず、口を閉じた。
村の奥から、数人の子どもがこちらに歩み寄ってきた。顔は土で汚れ、痩せた腕と脚は骨ばっている。だがその瞳だけは異様な光を帯びていた。
大人のような諦めと、獣のような飢えが混じり合った光。一人の子どもがデカルトの足元に近づき、彼の外套を引いた。
何かを呟いたが、その言葉は聞き取れなかった。ただ、その仕草と眼差しが、彼に突き刺さった。
デカルトはしゃがみ込み、子どもの瞳を覗き込んだ。
「君は……何を望むのだ?」
答えはなかった。子どもはただ、彼の手を握り、自分の胸に当てた。胸骨の下で鼓動がかすかに響いていた。飢えと疲れに弱まりながらも、確かに生きている心臓の音。
デカルトの喉が詰まった。理性は数式や論理を整えることはできる。
だが、この鼓動にどう応えるべきかを示すことはできなかった。
男の一人が近づき、かすれた声で言った。
「お前は……学者か、聖職者か。理屈を話すより、食べ物を持っているかどうか……だ……」
その直截な言葉に、デカルトは返す言葉を失った。
彼は確かに学者であり、理性を信じてきた。しかし、いま必要とされているのは理屈ではなく、ただの糧だった。
沈黙が流れた。人々の眼差しが彼に集まったが、それは期待ではなく、虚ろな諦めの光だった。
デカルトは外套を握りしめ、深く息を吐いた。
「私は……何も与えられない」
その言葉は、彼自身の心を突き刺した。
やがて人々は視線を外し、それぞれの小屋に戻っていった。
残された子どもたちも散り、静けさが戻る。
村を離れるとき、背後から微かな歌声が聞こえた。
老女が子どもを膝に抱き、掠れた声で子守唄を口ずさんでいた。
旋律は単純で、ほとんど囁きのようだったが、その中には確かな温もりがあった。
デカルトは立ち止まり、耳を澄ませた。理性では説明できないものがそこにあった。飢えも苦しみも消えはしない。だが歌は、束の間の心を支えていた。
「理性の言葉は届かなかった。だが、この歌は届いている」
彼はそう思いながら、再び歩き出した。
霧は薄れ、荒野が再び広がっていた。村の影は遠ざかり、風が彼の頬を冷たく撫でた。その冷たさは、彼に一つの問いを突きつけた。
「理性とは、人を救う光なのか。それとも、人と人の間に壁を築く影なのか」
答えは出なかった。ただ、その問いが彼の足をさらに荒野の奥へと運んでいった。
つづく…

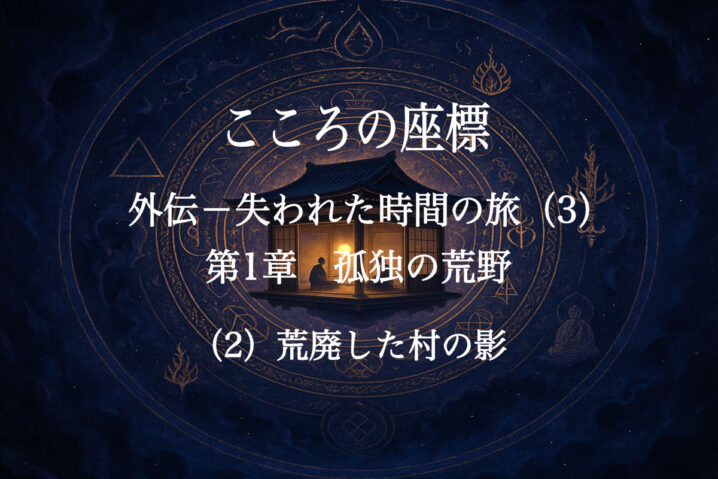





















コメントを残す