第1章 孤独の荒野
(1)霧と沈黙の中で
山の石段を下りきったとき、空気の質が変わった。そこには、音を吸い込み、匂いさえも曖昧にするような霧が漂っていた。
月は背後の峰に隠れ星々も霧の膜に覆われて、光はほとんど地上に届かない。
デカルトは外套の襟を立て、歩を進めた。足元の土は湿り、時折、靴底に小石が擦れる乾いた音がする。それ以外の音はなかった。
夜の森には、通常なら鳥や獣の気配があるはずだ。
だがここでは、それらの生命のざわめきがことごとく霧に呑み込まれている。
「我思う、ゆえに我あり」彼は小さく口に出してみた。
その言葉は、この数年、彼の思索を支え続けてきた確かな柱だった。
だが、声は霧に溶け、反響すら返ってこなかった。
自身の耳に届くその響きでさえ、どこか虚ろに感じられた。
「……しかし、聞く者がいなければ、この“我あり”は、ただ空気に刻まれるだけではないのか」
歩きながら彼は思った。人間の理性は、確かに普遍性を持つはずだ。
論証は人を越えて共有され、言葉は国境を超える。
けれど今この瞬間、自分以外にその思考を受け止める者は存在しない。
思索の輝きは、霧に吸われ、闇に散っていく。
周囲を見渡せば、地形は緩やかに開けていた。
樹木は少なく、低い草がところどころに群れているだけだった。
霧の密度は増し、先を歩むほどに白い壁が立ちはだかるように見えた。 風はなく、空気は重く滞っている。
遠くで水が流れるようなかすかな音がした。
川なのか、それとも霧が幻聴を生んだのか、確かめる術はない。
デカルトは立ち止まり、深く息を吸った。湿った空気が肺に入り込み、冷たさが胸の奥に広がる。
「孤独とは、思索を深めるための条件である。
だが……また……、孤独は思索の刃を鈍らせる」
声に出したその言葉は、自らの心を確かめるためであり、誰かに届くことを期待したものではなかった。
彼の歩みはゆっくりと続いた。やがて足元に崩れた石の列が現れた。
人の手で積まれたものか、自然に崩れたものかは分からない。
しかし、そこには「かつて人が居た痕跡」を感じさせた。
彼は石に触れてみた。表面はざらつき、指先に乾いた粉がついた。
その感触は、思索の世界とは異なる「現実」の確かさを示していた。
「人は石を積み、家を建て、共同体を築いた。
そして理性をもって協力し、自然に立ち向かった。
――だが、なぜその痕跡しか残っていないのか」
その問いは、霧の中へと吸い込まれていった。
返答はない。代わりに、胸の奥で空虚さが広がる。
歩を進めるほどに、孤独は濃くなっていく。
理性は彼に答えを与えるが、その答えは誰にも届かない。
「理性とは、光なのか。それとも、私をさらに孤独へ追いやる焔なのか……」
その瞬間、足元の石が崩れ、小さな音を立てた。
デカルトは一歩退き、深く息を吐いた。
霧の中で、自らの影さえ見失いそうになりながら、彼は再び歩みを続けた。
夜はまだ深く、荒野の輪郭は完全には姿を現していなかった。
だが彼の心には、すでに「孤独」という地形が刻まれていた。
つづく…

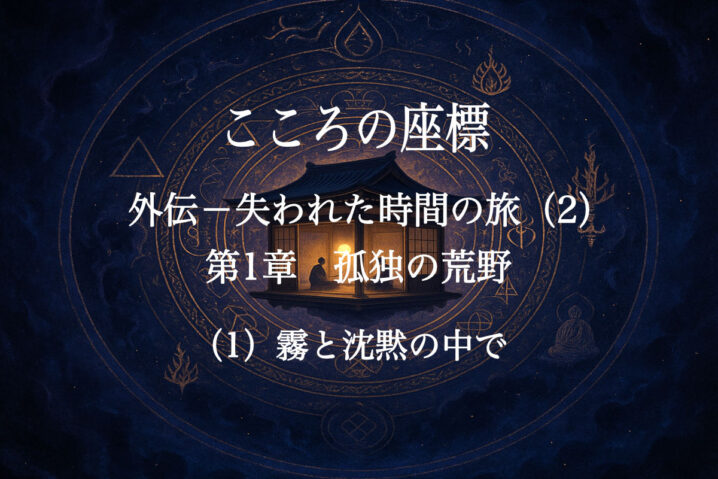























コメントを残す