(4)縁起の迷宮
曼荼羅の奥へと足を踏み入れた瞬間、デカルトの視界は不思議な揺らぎに包まれた。
壁に掛けられたはずの平面図は、もはや「絵」としての輪郭を失い、奥行きをもった回廊へと変容していく。
朱と群青が絡み合い、金と緑が波打ちながら道を形づくる。
迷宮は静かに彼を呑み込み、歩むごとに新しい通路が生成され、後方を振り返れば、先ほど通ったはずの道がすでに形を変えていた。
空海の姿はそばにあるようで、しかし距離感は一定しない。声は近くにも遠くにも響き、迷宮そのものから語りかけているようだった。
「幻ではありません。曼荼羅は、あなたの内にある縁起を映しているのです」
その声は、石畳にしみ込んだ水のように、彼の意識の奥へ届く。
進むうちに、光の門がふいに現れた。デカルトがためらいながら門をくぐると、そこに広がっていたのは幼少期の記憶だった。
母に手を引かれ、寒い教会の石床の上に座っている幼い自分。
ロウソクの炎はかすかに揺れ、光が高い天井に反射していた。
子どもだった彼は「神」という存在にまだ明確な像を持っていなかったが、同時にその見えぬものの前に、恐れと憧れを入り混ぜた素朴な感情を抱いていた。
その時の胸の震えが、今、迷宮の只中で甦る。
次に視界は移ろい、若き日の自分が机に向かう姿が現れた。
ランプの光の下、幾何学の図を広げ、推論を組み上げていく。
「理性こそが唯一の導き手だ」と信じ、夜を徹して論文を書き続ける。
だが、その背後にはいつも影のような不安が潜んでいた。
──私の論証を支える“基盤”はどこにあるのか。
論理を積み上げれば積み上げるほど、足元にぽっかりと空洞が口を開けている気がした。
その焦燥が胸を刺し続けていたことを、彼は今さらながら痛感した。
さらに奥へ進むと、未来の影が浮かび上がった。
老いた自分が書物に囲まれ、深い沈黙の中でただ一人祈っている姿。
窓の外には薄い光が差し、背後の壁には曼荼羅の模様が淡く投影されている。
その姿は孤独であると同時に、不可思議な安らぎも宿していた。
──これは予兆なのか、それともいまここで編まれた幻なのか。
彼には判別できなかった。だが、その像を見つめると、未来さえもまた流動する縁の網の一部であると直感する。
デカルトは立ち止まり、胸に手を当てた。
「私は……“私”であるのか?」
その問いは霧となり、回廊の天井へと昇っていった。
空海の声が答える。
「あなたは孤立した点ではありません。縁の網の中の結び目です。
あなたが“私”と呼ぶものは、過去や未来の無数の縁によって支えられ、いまここに立ち現れています。
自己とは、つねに編み直される関係の結び目なのです」
その言葉に、デカルトの胸の奥で何かがほどけた。
彼はずっと、「我思う、ゆえに我あり」という確固とした中心を支えにしてきた。
だが曼荼羅の迷宮は、中心を解体し、流動する関係の中に自己6を置き直すことを迫っている。
不安は消えない。だが、その不安さえも、網の一部として抱え込まれていく。
回廊の壁に並ぶ仏たちは、微笑みを浮かべていた。
その微笑みは彼を裁くものではなく、不安も迷いもそのまま肯定し、さらに奥へ進ませる力を与えていた。
まるで彼自身が曼荼羅の中の一尊であり、網の中で生滅を繰り返す存在であることを示しているかのようであった。
歩を進めるほどに、彼は「時間」という概念の輪郭も失っていった。
幼少の自分も、青年期の自分も、未来の自分も、同時にここに在る。
過去は過ぎ去るものではなく、未来はこれから来るものではなく、すべてが「縁起の迷宮」の一節として共存している。
デカルトは深く息を吐き、静かに目を閉じた。
そこにあるのは、流動する自己同一性──固定された「私」ではなく、編み直され続ける「私」の網だった。
つづく…



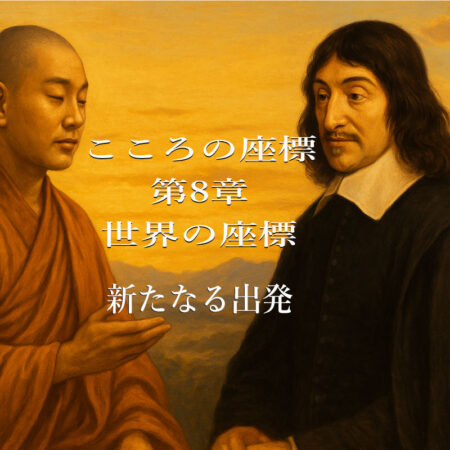

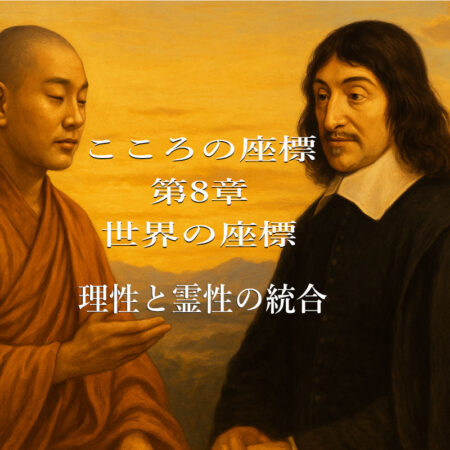

























コメントを残す