(2)曼荼羅の門(後編)
足を踏み出した先で、床板の響きが変わった。低く長い、洞窟の奥へ吸い込まれていくような音。
視界の奥、曼荼羅の色面がわずかに膨らみ、遠近の感覚が反転する。平面に見えたものが、からだの内側へと沈んでいく階段に変わり、逆に自分の背後の空間は、薄い紙のように平坦になっていく。
「怖れることはありません」
空海の声が、一定の間まを保ちながら届く。
「いまあなたが経験しているのは、視覚の秩序ではなく、関係の秩序です」
デカルトは片手を胸に当て、脈の落ち着きを確かめた。鼓動は速いが乱れてはいない。
もう一歩踏み出すと、曼荼羅の一隅で、金剛杵を持つ尊の眼差しがこちらへ向く。絵具の粒立ちは見えるのに、その視線は人のもののように生々しい。
否、それは「視線」ではない。網の目の一点が、別の一点を迎え入れる時に生じる応答──かすかな張力だ。
「私は、見られているのですか」
「あなたが“見ている”のと同じ仕方で」
空海は袖を整えながら続けた。
「見る、見られるは、ここでは二つに分かれていません」
堂内の香煙が細い螺旋を描き、曼荼羅の色を撫でる。
朱の上では温い霞、群青の上では冷たい霧になる。あらゆる色が、それぞれ固有の手触りを持ち、視覚のはずが触覚の記憶を呼び覚ます。
デカルトは、視線を一点に固定するのをやめ、緩やかな輪を描くように撫でる。
中心と思しき円座、そこから外環へ、さらに対角に渡る金剛界の線。
彼はふと、学僧が示した幾つかの印いんに目を留める。指は結ばれ、ほどかれ、また結ばれる。
呼吸と指先のわずかな動きが、曼荼羅の図形を音のない言語でなぞっている。
「その印は、何を意味するのです」
「結び目です。存在と存在の結び目。ほどいては結び、結んでは渡す。その動きが世界を“いま”へ保ちます」
ほどく、結ぶ。
デカルトの脳裏に、数学の証明で用いた補助線や、論証を支える推論の結合が次々と浮かぶ。
しかしここでは、結合が証明の終点に収斂するのではなく、流動する場を保つために結ばれ続けている。
灯明の炎がひときわ大きく揺れ、曼荼羅のある区画に、微かに銀の光が差した。
そこでは、微細な梵字が連なり、絹の地に水面の波紋のような重なりをつくっている。
目を凝らすと、一つひとつの梵字が、別の文字の影を宿し、単独で完結しないように見える。
「文字が、互いに影を持つ……」
「音の殻が重なり合っているのです」
空海は、ほとんど囁きに近い声で言った。
「言葉は固定ではなく、縁起の合奏です。ここでは、名は対象を縛らず、対象は名に閉じこめられない」
デカルトは、思想史の記憶の底に沈む厳密な定義の数々を思い出す。
定義は鋭利だ。鋭利であるほど、切断は明快だ。
だが切断の境目の“薄さ”が、いまは奇妙に心細い。
この曼荼羅が提示するものは、切断の線よりも、結び目の太さ、撓み、伸縮、そして線が線であることを保ちながら線であることをやめていく、あの移行の柔らかさだ。
空海は灯明の高さを少し下げる。光源が下がると、曼荼羅の高低の錯覚が逆転する。
高みにあったはずの区画が沈み、遠かったはずの像が手前にせり出す。
視点の移動ではなく、視座そのものが微かに組み替えられていく。
「理性は、何を捨てるべきでしょう」
デカルトが問う。
「捨てる、ではありません」
空海は首を横に振った。
「並べるのです。理性の隣に感覚を、感覚の隣に沈黙を。沈黙の隣に、祈りを。
隣り合うものは、互いを否定せず、互いを正す。曼荼羅はその“隣”の設計図です」
隣り合う──。
彼は、幾何学の証明で補助線が作る“隣接”を思う。
ここでの隣は、距離の近さよりも、時の重なり、意味の往還、気配の行き来で定義されるらしい。
距離の無い隣接。時間の厚みだけが隣をつくる。
堂外から、ひとしずく雨が落ちる音がした。
続いて、屋根の端を叩く連続音。
雨粒の生む微細なリズムが、曼荼羅の幾何の拍に重なり、見えない譜面がゆっくりと展がる。
デカルトは、胸の内に小さな拍子木が置かれたように感じた。刻みは一定だが、打たれるたびに、その一定がわずかに広がり、戻り、また広がる。
「私は、中心を探してしまう」
彼は正直に告げた。
「どれほど視線を泳がせても、心はどこか一点に拠りたくなる。そこに、確かさを置きたいのです」
「中心は、器であって、石ではありません」
空海は視線で曼荼羅の核を示した。
「器は、満ちては空き、空いては満ちます。
あなたが“中心”と呼ぶものは、固定ではなく、受け渡しの場なのです」
受け渡し──。
彼は、師と弟子、問いと答え、命題と証明のあいだを流れる目に見えない時間を思い描く。
受け渡しの場ならば、中心は一点ではなく、連鎖する“時”の厚みであるはずだ。
確かさは、釘のように打ち込まないのだ。
確かさは、呼吸のように保つのだ。
空海は、曼荼羅の手前に小さな敷物を広げ、座を促した。
デカルトが座すると、床の固さが素直に背骨を支え、腰のどこにも余計な力が入らないことに気づく。
呼吸が自然に長くなり、吸う息と吐く息の間が、これまでよりも少し広い。
「目を閉じ、曼荼羅を閉じないでください」
空海の指示は矛盾をはらんでいるが、身体はためらわずにそれに従う。
目蓋の裏で、さきほどの群青が、今度は深い井戸の底の影として立ち上がる。
朱は井戸の縁に張り付いた温度になり、金は、喉の奥で転がる小さな丸薬のように存在感を持つ。
音が戻ってくる。
雨は少し強くなった。
堂内の空気は、濡れた土の匂いを含み、香の甘さと重なって、遠い記憶をひとつ呼び寄せる。
幼い日の朝、湿った石畳の匂い。
その上を渡る自分の影。
影は、当時の自分よりも静かに歩いた。
「記憶が、勝手に」
「縁が触れると、記憶は来ます」
空海の声は近い。
「来たものを追わず、来ないものを待たない。
ただ、“来る”を受け入れ、“去る”を見送る。その間あいだに、曼荼羅は成り立ちます」
デカルトは眼を開けた。
曼荼羅は、たしかに“変わっていない”のに、まるで別の顔を持っている。
ひとつの像の輪郭が、別の像の余白として浮かび、余白は余白のまま意味を孕む。
彼は、余白に向けて小さく頷いた。
そこに、何かが在る。
「私は、ようやく、ここが“門”であるとわかりかけています」
「門を“越える”のではありません」
空海は微笑を含む。
「門は、通過点であり続ける。中に居ながら、つねに門に立ちます。
境が消えるのではない。境が、境であることをやめないまま、渡し舟になるのです」
雨脚がさらに強まる。
堂の軒から落ちる水は、糸から紐へ、紐から帯へと太さを変え、地面に音の円を描く。
円は重なり、ほどけ、消える。
デカルトは、その消え際に耳を澄ました。
消える直前の、かすかな持続。
無音の手前で起こる、音の最後の仕事。
「空海、私の理性は、いま、抵抗していません。
けれど、理解と言ってよいのかどうか、判断がつきません」
「判断は、橋の中央には要りません」
空海は、手元の数珠を一度だけころんと転がした。
「こちら岸と向こう岸が、互いを指し合う場に、正誤の札ふだは立たない。
ここで必要なのは、渡る歩幅を保つことです」
デカルトは息を吐く。
歩幅、という言葉が、からだにすっと入る。
そして、彼はゆっくりと立ち上がった。
曼荼羅の前に、二歩、三歩。
距離はほとんど変わらないのに、近づいていく感覚だけが確かに増える。
「あなたは、いま“読む”のをやめました」
空海は静かに告げる。
「これからは、“歩む”の番です」
曼荼羅に、掌を向ける。
触れてはいない。だが、掌の内側に、冷たい気流のような微かな動きが当たる。
その向こう側から、同じ強さでこちらへ向かう流れが返ってくる。
往と還。
押しと引き。
問と応。
彼は掌を引き、胸の前で合わせた。
印ではない。未熟で、たどたどしい、しかし確かめるような両掌の合掌。
その瞬間、曼荼羅の中心で、ひときわ小さな灯がひらめき、すぐに消えた。
ひらめきは、印ではなく、合図でもない。
ただ、歩幅が合ったときに自然に生じる、ささやかな同期。
デカルトは空海の方を見ず、視線を曼荼羅に置いたまま、短く言った。
「ここから先を──お願いします」
空海は軽くうなずく気配だけを残し、声を落とした。
「では、“色即是空”の入口へ。
形は空で、空は形。
あなたの歩幅で、確かめましょう」
雨はいつのまにか細くなっていた。
堂内の空気は澄み、香の筋はまっすぐに伸びる。
曼荼羅の色は、先ほどよりも淡いのに、輪郭は深く、遠いのに近い。
門は、ひっそりと開いたまま、彼らを見送っている。
つづく…
【速報:近日公開】
長編連載小説 『こころの座標』外伝―失われた時間の旅
もし、あのとき時の流れがほんのわずかでも違っていたなら、
ふたりは何を選び、どこへ向かっていたのだろうか――。
これは、「存在の座標」をめぐる旅の、もうひとつの物語。
かつて交わることのなかった時空のしじまに、
失われたはずの声が、かすかに響きはじめる。
空海は、夢のように崩れゆく過去の中で、
“永遠”と“刹那”が重なる地点を探し続ける。
デカルトは、記憶の迷宮をさまよいながら、
そこに“思考”の始まりと終わりを見出そうとする。
阿修羅の怒り、弥勒の微笑、
そして釈迦の沈黙にふれるたび、
ふたりの魂は時空の裂け目に吸い込まれ、
やがて――“存在の秘密”に触れてゆく。
次元を超えた、内なる巡礼の旅。
それは、未来を変えるための、過去への回帰。
『こころの座標』、沈黙のその先へ。
長編連載小説『こころの座標』外伝―失われた時間の旅
2025年09月17日 21:00 連載開始
【次回予告】
あらゆるものが織りなす曼荼羅の網の目に、
ふたりの視界は、次第に深い構造を見はじめる。
触れられるもの、見えるもの、思うことすら――
すべては、空なるものから生まれ、
また空へと還ってゆく。
空海の語る「色即是空」は、ただの言葉ではない。
それは世界の骨組みであり、
生と死のあわいに立つ者たちが見る、
透明な真実のかたち。
デカルトは問いかける。
「形なきものは、どうして形あるものを支えるのか?」
その問いの先に浮かぶのは、思考を超えた〈在る〉という静かな確信。
次回、ふたりは“空”の構造そのものに触れる。
世界が形を変えていく、その一瞬をご一緒に。
長編連載小説『こころの座標』(18)第七章 色即是空の構造―③
2025年09月13日 21:00 公開

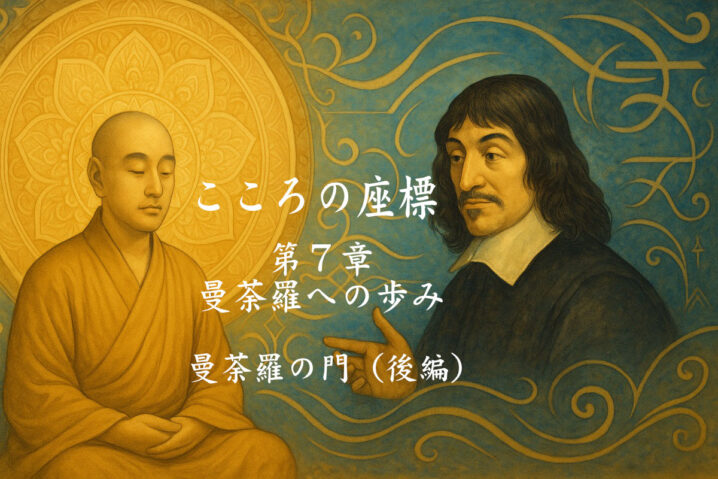
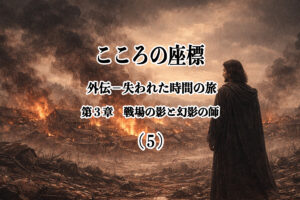
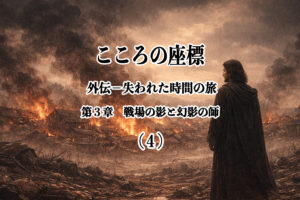


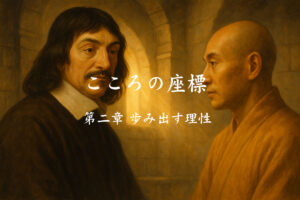
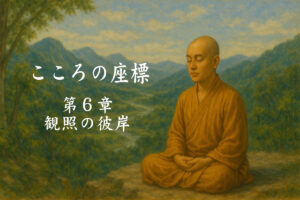
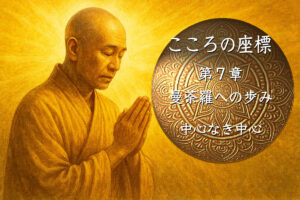
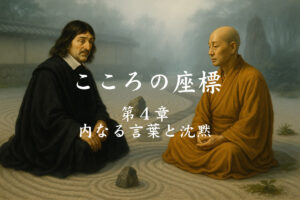
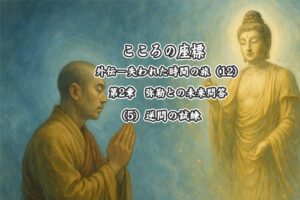
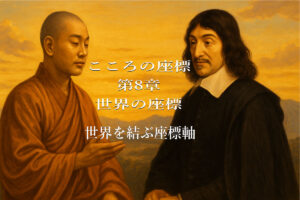






コメントを残す