(4)言葉を超えて伝わるもの
午後の陽が傾きはじめたころ、ふたりは庵を出て、小径を歩いていた。樹々の間から漏れる光は斜めに伸び、葉に映った影はゆらゆらと揺れている。空は高く、蝉の声が遠くから聞こえていた。
「あなたの言葉には、形がある」
空海がふいに言った。
「形……ですか?」
デカルトは歩を緩めた。
「はい。あなたの語る言葉は、輪郭がはっきりしている。それはまるで、彫刻された像のようです。理性によって磨かれ、意味の輪郭が際立っています」
「……それは、私の訓練の成果かもしれません。曖昧な観念を嫌い、できる限り厳密な定義と論理で世界を描こうとしてきました」
「その努力は、尊いものです」
空海は立ち止まり、木漏れ日の中に手をかざす。
「ですが、“形なきもの”が存在することも、否定はできぬでしょう」
「たしかに。私は今、まさにその“輪郭の外”にあるものに直面している。言葉で掴みきれない、けれど確かにそこに在る何か……」
空海は、静かに右手を胸の前に掲げ、親指と人差し指で印を結んだ。
「これは“智拳印”と申します」
デカルトは、空海の手に注目した。指の形、手の動き、それに込められた意味。言葉は発されなかったが、空気が変わった。
「密教では、印(ムドラー)を結ぶことで、仏の智慧や慈悲を身体に映し出します。これは“言葉ではない言語”です。身が語る――これを“身語”と呼びます」
「身が語る……?」
「はい。仏は、三つの方法で我らに示されるとされます。“身”=形の表現、“口”=言葉、“意”=思念。この三つを三密と言います。そして、我ら修行者はその三密をもって仏と一体となることを目指すのです」
デカルトは驚きと関心をあらわにした。
「つまり……あなたがいま行った“印”は、言葉を超えた対話の形だと?」
「そうです。言葉が通じぬ者とも、印は通じます。たとえば、泣く子をあやす母の手つきは、言葉ではありませんが、子はそれを全身で理解する。それは“ことば”ではなく、“存在そのものの伝達”です」
デカルトは、思い出したようにひとつの出来事を語った。
「ある日、私は病床の母の手を握ったことがあります。言葉は交わせませんでしたが、その手の温かさが、私の中の何かを確かに動かしました。いま思えば、あれが“言葉を超える伝達”だったのかもしれません」
空海は黙って頷いた。
「あなたの語る哲学が、世界を整える言葉の道ならば、我らの修行は、“沈黙の行”とも言えるでしょう。身体で祈り、空を体感し、言葉以前の世界に触れる」
「では、そのような伝達は、理性の検証には耐えられないのではありませんか?」
「逆に申せば――理性の及ばぬところにこそ、実在が潜んでいるとも言えましょう」
ふたりはまた歩き出した。周囲には人の気配はなく、ただ森と空と、風の音があった。
「印を交わすとき、それが意味するものは何ですか?」
デカルトが問うた。
「それは“共鳴”です。仏と一体になるということは、仏の響きと“合わさる”こと。そのとき、言葉では伝えられぬ慈悲や智慧が、身体を通して届くのです」
「あなたは、私に印を結んでみせた。それは、何を伝えようとしたのですか?」
空海は、木々の間から差す光を仰ぎながら、静かに答えた。
「あなたの内なる沈黙にも、すでに仏の響きが宿っている。それを忘れないでほしいということです」
ふたりのあいだに、再び言葉は途絶えた。
だがその沈黙は、深く、澄んでいた。
風が、木の葉を揺らす。
それは、声なき言語のように、二人の間を渡っていった。
(5)無言の了解と真の対話
空が朱に染まりはじめた。西の山並みに夕日が差し込み、森の影は長く伸びていた。ふたりは山道を抜け、小高い岩場に出ていた。そこからは、深い谷と遠く連なる峰々が一望できた。風が吹き抜け、涼やかな音を運んできた。
空海はひとつの岩に腰を下ろし、深く息を吸った。
デカルトも隣に座る。しばし無言のまま、二人は夕暮れの風景に見入っていた。
誰も語らなかった。けれど、不思議と、何かが語られているようだった。
その沈黙は、重くもなく、空虚でもない。むしろ、深く澄んでいた。
まるで長い対話を終えたあとのような、静かな満足感がそこにあった。
やがて、デカルトがぽつりと口を開いた。
「言葉は、いつしか言葉を離れるのですね」
空海は目を閉じ、頷いた。
「はい。そしてそのとき初めて、言葉は本当に“伝わる”のかもしれません」
「私は、真理に近づこうとして、言葉を極限まで削り、整え、鍛えてきました。それでも、触れることのできない領域がある。それは、単なる“曖昧”ではなく、むしろ“最も澄んだ沈黙”なのかもしれません」
「沈黙とは、“語らぬこと”ではありません。“語りえぬこと”を、静かに包む器です」
デカルトは頷きながら、両手を膝の上に置いた。
「もし哲学とは、“世界を解き明かす”営みだとするなら、私はこう問わねばならない。“語らずして、どう真理に触れ得るか?”と。しかし今の私は、逆にこう問いたい。“語ることによって、どれほど真理を見失ってきたか?”と」
「それこそが、対話の実りでしょう」
空海の目は、夕日に照らされて穏やかに光っていた。
「仏教において、“悟り”とは何かと問われるなら、それは“了解”と答えるかもしれません。理解ではなく、了解――共に領ること。つまり、共に在るということです」
「共に在る……それは、言葉よりも深い結びつきだ」
「そうです。母が子を抱くとき、友が友を見つめるとき、老いた者が空を仰ぐとき――そこに言葉はなくとも、了解はある」
「なるほど。真の対話とは、相手の論理を理解することではなく、相手の“在り方”に共鳴することかもしれませんね」
ふたりは沈黙した。
だがそれは、もう何も語る必要がないという沈黙だった。
言葉が尽きたのではない。深いところへ言葉が届いたのだ。
日が沈み、空に一番星が現れた。
「空海殿、私は今日、思考の海を越えたように思います。いや、正確には……その海の広さを初めて感じることができたのかもしれません」
「そしてあなたの声は、すでに沈黙の中で響いています」
デカルトは、やわらかく微笑んだ。
「あなたの語りは、私の哲学の余白に、静かに灯をともしてくれたようです」
「私にとっても、理を生きるという姿が、こんなにも澄んだものだと教えられました。理性と祈りは、対立ではなく、交差するものなのですね」
風が吹いた。
草の上を、葉がひとひら舞った。
空海は合掌し、静かに礼をした。デカルトもまた、それに倣って深く頭を下げた。
そこに言葉はなかった。ただ、静けさの中に宿る、祈りのような了解があった。
ふたりは、ゆっくりと立ち上がった。
西の空は紫に染まり、夜が始まろうとしていた。
つづく…
次回投稿 小説「ここの座標」(9)ーー 第5章 救済と理性 ①
2025年07月19日(土) 21:00 公開
#こころの座標
#哲学対話
#デカルト
#空海
#仏教思想
#西洋哲学
#東洋思想
#理性と慈悲
#哲学好きと繋がりたい
#仏教と哲学
#哲学創作小説
#創作小説
#思想小説
#文学作品
#対話劇
#物語の力
#言葉と沈黙
#フィクション
#心の物語

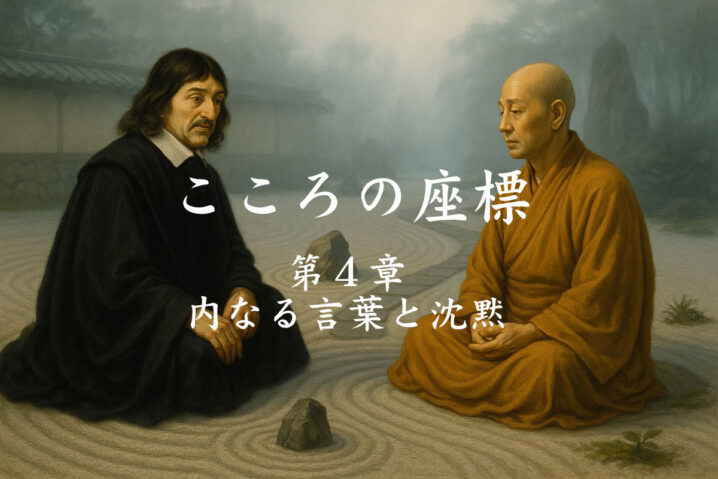


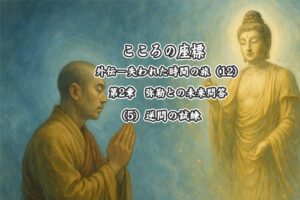
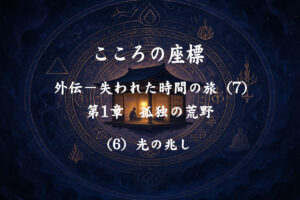
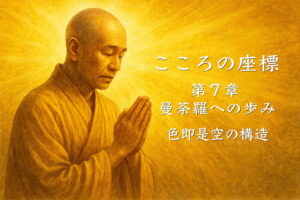
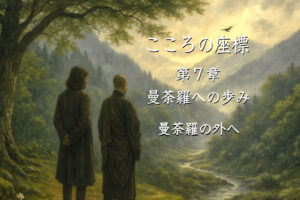
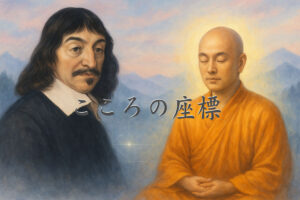
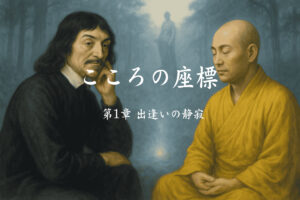
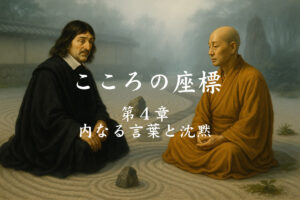
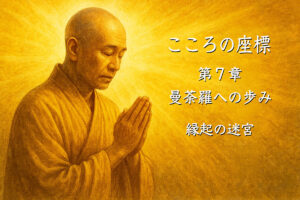
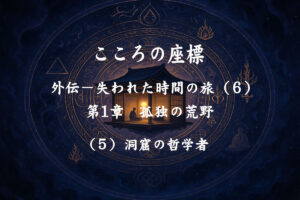
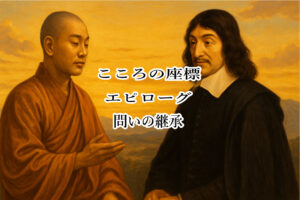










コメントを残す