(1)曼荼羅の門(前編)
山の奥深く、木々の葉が秋色に染まりかけた頃、朝の霧がゆっくりと谷間を下りていく。 その霧の中を、デカルトと空海は並んで歩いていた。足元の石段は苔むし、しっとりと湿り気を帯びている。踏みしめるたびに、静な音が霧の奥に吸い込まれていった。
やがて石段が終わり、視界の先に重厚な木の扉が現れた。扉は漆黒に塗られ、金色の金具が四隅を飾っている。そこに描かれた円文と蓮の花は、時を経てもなお鮮やかで、まるで深い呼吸をしているかのように見えた。
「ここが曼荼羅の門です」 空海はそう言って立ち止まり、両の掌を静かに合わせた。
デカルトは扉を見つめながら、理性が即座に分析を始めるのを感じた。幾何学的な構成、形の配置、色彩のバランス──それらは人の意図によって配置された明確な秩序を示している。しかし、彼は同時に、その秩序の奥に、計算だけでは捉えきれない流動的な「何か」が潜んでいる気配を感じた。
「これは……図像ですか、それとも儀礼の道具なのですか?」 問いかける声は慎重で、だが内心の興奮を隠しきれていなかった。
「どちらでもあり、どちらでもありません」 空海は微笑み、扉に手をかける。「曼荼羅は読むものではなく、歩むものです」
その言葉に、デカルトの眉がわずかに動いた。 読むのではなく、歩む──。 論文や図面を読むことには慣れているが、「歩む」図という概念は初めてだった。
重い扉が静かに開かれると、香木の甘く深い香りが押し寄せてきた。室内は薄暗く、奥の壁一面に巨大な曼荼羅が広がっている。金、朱、群青、緑──数えきれぬほどの色彩が、きらめきと沈黙のあいだで呼吸しているように見える。
デカルトは思わず一歩足を踏み入れた。その瞬間、足元の板の感触が変わり、空間の音の響きも変化した。天井の梁に反射する声明の余韻が、曼荼羅の色彩と溶け合っているようだった。
「あなたの眼は、いま曼荼羅の縁に立っています」 空海の声が背後から届く。「これからあなたが進むのは、紙や絹に描かれた平面の中ではなく、存在の構造そのものです」
デカルトは曼荼羅を凝視した。そこには、中心から放射状に広がる幾何学的なパターンがあり、円環が重なり合い、複雑な階層を成していた。それは宇宙の地図にも、思考の回路図にも見える。しかし、観れば観るほど、その形は微妙に変化し、固定された輪郭を持たないように感じられた。
「……形が、動いている」
「はい。曼荼羅はあなたの心の動きに応じて姿を変えます。これは単なる視覚の錯覚ではありません。あなたの内面が変化し、縁起の糸が結び直されているのです」
デカルトは、理性と感覚のあいだで揺れていた。 彼の訓練された眼は、パターンの規則性を見出そうとする。だが同時に、香の匂い、柔らかな光、わずかな空気の流れ──五感の全てが一つの「場」に溶け合い、論理だけでは測れない感覚を生んでいる。
空海は曼荼羅の手前に座し、掌を膝の上に置いた。「デカルト、あなたはこれまで『我思う、ゆえに我あり』と唱え、理性を礎として世界を理解しようとしてきました。けれど、曼荼羅の門をくぐるとき、その“我”は中心ではなく、網の目の中の一節になります」
「網の目の中の……一節?」
「そうです。あなたは糸全体の一部であり、その全体もまたあなたの中にある。曼荼羅はその関係性を示す鏡なのです」
デカルトは視線を曼荼羅から外そうとしたが、できなかった。 色彩がゆらぎ、形が重なり、中心が無限に増殖する。目の奥で、思考と感覚が交差する地点が熱を帯びていく。
「では、この曼荼羅を読み解くことは……」
「読み解くことではなく、歩み入ることです。読む者は対象を外から眺めますが、歩む者は対象の一部となります」
空海の言葉は、デカルトの論理の地盤を静かに揺らした。 曼荼羅の門──それは物理的な扉だけでなく、彼の心に開かれつつある新しい世界の入り口だった。
堂内の空気は、外界と隔絶されたように重く、しかし不快ではなかった。むしろ、そこに満ちているのは深い湖の底に漂うような|静謐《せいひつ》だった。 外から差し込む光はほとんどなく、灯明の炎がゆらゆらと揺れながら、曼荼羅の一部を黄金色に染めている。その光は、ある時は山の稜線のように見え、またある時は雲間から差し込む天光のように見えた。
デカルトは、その光と影の変化をじっと観察した。 彼の思考は、いつものように対象を「要素」に分解しようとする。炎の揺らぎ、色の反射、構図の対称性……しかし、それらを分解しようとすればするほど、全体が新たな形をとって立ち現れる。まるで、部分を追えば追うほど全体が姿を変えてしまうようだった。
「空海、これは……なぜこんなにも変化して見えるのですか?」 問いは純粋な驚きから発せられた。
「あなたの眼が変化しているからです」
「眼が……?」
「曼荼羅は、あなたの心を映す鏡です。理性が優位に立てば幾何学模様として見え、感覚が広がれば色彩の海として現れます。そして心が静まれば、そのすべてが一つに融けます」
デカルトは再び曼荼羅を見つめた。そこには無数の仏や菩薩の姿が描かれ、宝相華が咲き乱れ、金剛杵が放射線状に広がっていた。それぞれの位置は厳密に定められているようでありながら、その間に漂う空間には不思議な柔らかさがあった。 数学の図形ならば、点と点は線で結ばれ、線と線は面を形づくる。しかし、曼荼羅の中では、点と点の間に「間」があり、その「間」が形を生み出していた。
「この“間”……これは、私の論理には存在しないものだ」
「それが、東洋で“縁起”と呼ばれるものです」 空海は穏やかに言葉を継いだ。「存在は単独で成り立つのではなく、他との関係の網の中でのみ成り立ちます。曼荼羅はその網の地図です。ですから、あなたが一点を見つめる時、その周囲のすべてが共に変化します」
デカルトは呼吸を整え、目を閉じてみた。 すると、香の匂いがいっそう鮮明に意識に上ってくる。甘く、木の皮のような乾いた香りが鼻腔を満たし、深呼吸のたびに胸の奥まで広がっていく。耳を澄ますと、堂外の小さな水音や、木々の葉が揺れる音までもが曼荼羅の一部のように感じられた。
「……外の音までが、この図の中にあるようだ」
「それもまた真実です。曼荼羅は堂内の壁に限られたものではありません。あなたが一歩外に出ても、石段も、川のせせらぎも、鳥の声も、そのすべてが曼荼羅の延長です」
その言葉を聞いた瞬間、デカルトの中で何かがほどける音がした。 理性は常に「対象」と「自己」を分けてきた。対象を外側から観察し、自己は観察者としての立場を保つ。しかし、空海の語る曼荼羅は、その境界を静かに消していく。観察者と対象が同じ網の目の中にあるのだとすれば、「外側」など存在しないことになる。
デカルトは少しふらつくような感覚を覚え、思わず壁際に手を添えた。 壁の木肌は温かく、手のひらにわずかな脈動のようなものを感じる。まるで堂そのものが生きているかのようだ。
「空海……私は、これまで“知”の門を叩いてきました。しかし、これは……知識ではなく、何かもっと広くて深いものの入口のように感じます」
「それが“曼荼羅の門”です」 空海はゆっくりと立ち上がり、デカルトの隣に並んだ。「ここから先は、あなたの理性だけでは進めません。感覚と理性、沈黙と語り、そのすべてを携えて進むのです」
灯明の炎が再び揺れた。 その揺れの中で、曼荼羅の中心から微かな光が放たれたように見えた。 デカルトは息を呑み、その光を追おうとした。しかし光は彼を導くようにゆっくりと形を変え、中心から外縁へ、外縁からまた中心へと円を描いて巡っていく。
一歩め。 言葉にならぬ声が、曼荼羅の奥から響いた気がした。
彼は一歩、曼荼羅に向かって足を踏み出した。
つづく…

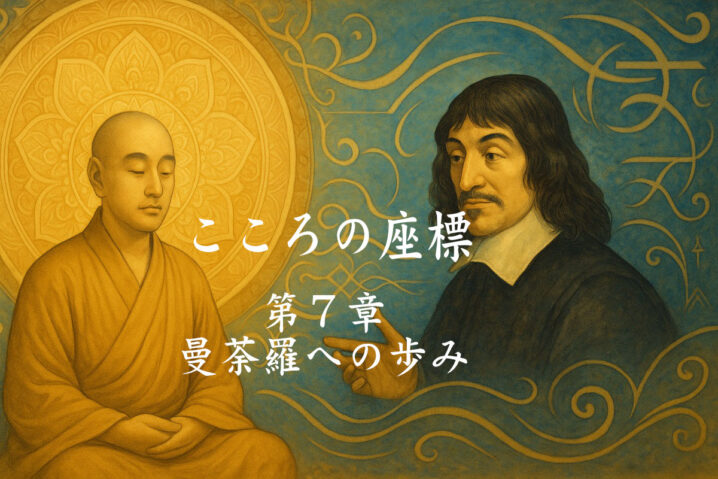
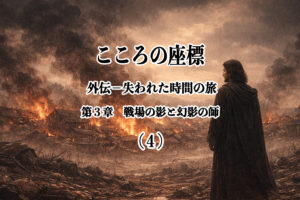


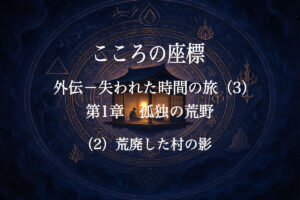
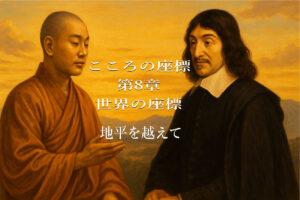
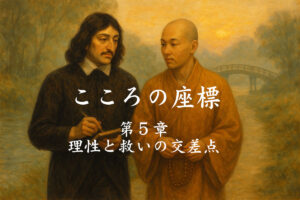
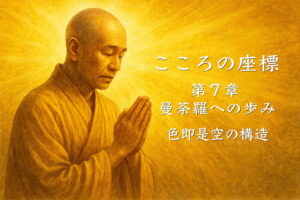
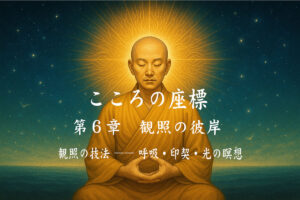
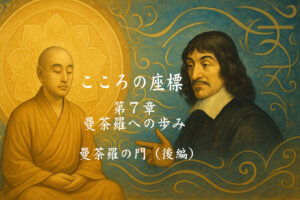









コメントを残す