(1)沈黙に宿る声――言語と思考の限界、無言の理解
夜が静かに明けようとしていた。山の斜面には濃い霧が立ちこめ、あらゆる輪郭を白くぼかしている。草木は微かに濡れ、ひとつひとつの葉に夜露が宿っていた。風はない。全てが沈黙のなかに在った。
空海は、焚火の前に坐していた。薪の爆ぜる音が、かすかに空間を揺らす。それ以外に聞こえるものは、なかった。静寂が、むしろ音を際立たせる。焚火の煙が立ち上り、霧のなかでその形を見失う。
やや離れて、デカルトも同じように座っていた。彼の目は、炎を見ているようでいて、その奥にある何かを捉えようとしているようだった。二人のあいだに言葉はなかった。しかし、重なる沈黙が、何かを語っているようだった。
「言葉が……要らぬように感じますな」 空海が、ぽつりと漏らした。
その声は、周囲の沈黙に溶けこみながら、確かに届いた。まるで、静寂の奥底から湧き上がった泉の水のように、清らかで透明だった。
「言葉が要らぬ……?」 デカルトは目を細めて問い返した。だがその声には、反論や疑念ではなく、むしろ共鳴のようなものが宿っていた。
「はい。……いえ、正確には、“要らぬように感じる”だけで、実際はこうして、私はあなたに言葉で語っておりますが……」 空海は笑った。その微笑は、揺れる火影のように、やわらかく揺れていた。
「ですが、言葉を交わさずとも、今ここにある静寂が、すでに我々に多くを語っているように思えます」
デカルトはしばらく黙っていた。火を見つめていた視線を、ゆっくりと空海へ移す。
「私はかつて、言葉によって思考を明晰にし、概念を整理し、それによって真理を見出そうとしてきました。言葉がなければ、理性も形をとれぬのではないかとすら考えています」
「まことに、理性は言葉を通して形を成します。それはひとつの真理でありましょう」
「ですが……その理性が、沈黙の前で立ちすくむ時がある」 デカルトの声が、少し揺れた。
「理性では届かぬ何か。言葉に変換できない、だが確かに在るという感覚。それに触れたとき、私は、自分の哲学が……まだ始まりにすら至っていなかったのではないか……と感じるのです」
火の粉が、ぱちんと弾けた。
空海は頷いた。
「言葉を尽くせば尽くすほど、言葉にならぬものが立ち現れてくる。そのとき、我々は初めて、“沈黙に宿る声”に耳を澄ませることができます」
「沈黙に、声が宿る……か……」
「はい。言葉にならぬ声は、理屈ではなく、響きとして伝わります。たとえば祈りや、涙、あるいはただそばに”在る”ということすら、それに近いものです」
「私には……それが難しい」 デカルトは、少しうつむいた。
「私は言葉を鍛えてきた。定義と証明、推論と命題。だがあなたの言う“声なき声”は、私のその努力の網をすり抜けていく」
「それは、鍛えた言葉の証です。鍛えられた剣ほど、切れぬものの存在に気づくものです」
空海のまなざしは、焚火ではなく、霧に包まれた山の奥を見ていた。 それは、目には見えぬ何かを感じ取るかのようであった。 空海は静かに言う。「沈黙は、ただの“無”ではありません。何もないのではなく、あらゆる“もの”が、いまだ分化されぬまま、そこに潜んでいるのです。まるで、種子が咲く前の大地のように……」
その言葉に、デカルトは静かに目を閉じた。
焚火の温もりが、彼の頬を撫でる。
沈黙とは、逃げることではない。
沈黙とは、満ちることである。
そう――言葉の影には、言葉にならぬ思いが常に寄り添っている。沈黙はそれらを包み込み、抱擁するための器なのだ。
その夜、ふたりの間に、ほとんど言葉は交わされなかった。
しかしそれは、かつてないほど豊かな対話だった。
沈黙が声を持ち、火が言葉となり、霧が思考の余白を広げていた。
空が白みはじめ、鳥が一羽、霧のなかを横切った。
(2)言葉の輪郭と思考の海
太陽は、まだ山の向こうに姿を現していなかった。けれども、霧は少しずつ薄らぎ、空の色も夜の黒から、青みがかった銀へと変わりはじめていた。
デカルトと空海は、火の名残を後にして、湿った草を踏みしめながら緩やかな丘の上へ向かって歩いていた。露を帯びた草が、二人の足音を吸い込む。あたりは静かで、すべてが語りかけるように思えた。
「空海殿、私は一つ、問いを抱えています」 デカルトが立ち止まり、朝露に濡れた大地に視線を落とした。
「どうぞ」 空海は立ち止まり、ゆるやかに振り返った。
「“私は考える、ゆえに私はある”――この命題は、私の哲学の基盤です。ですが、この思考すらも、言語の助けを借りている。果たして、言葉がなければ、我々は思考することができるのだろうか?」
空海は、しばし黙した。そして、そっと歩みを再開した。
「言葉がなければ、思考もまた海のように、かたちを持たず漂うかもしれません。しかし、それは“思考していない”ことと同義ではないでしょう」
「つまり、言葉は思考を定着させる“容器”のようなものであって、思考そのものではない……と?」
「はい。容器の形に合わせて、思考は一部を映し出します。しかしその水源は、もっと深く、静かなところに在るのです」
デカルトは頷いたが、どこか納得しきれぬ様子であった。
「しかし、容器がなければ、我々はその水を他者と分かち合うことができません。だからこそ私は、明晰な言葉による定義を求め、曖昧な感覚や印象を排除してきました。だが……それでも消えずに残る“名づけようのない何か”が、いつも私の哲学の背後に、影のように立ち続けているのです」
空海は足を止め、振り返った。そして、ゆっくりと手を広げて朝の霧の中の山々を示した。
「それこそが、“言葉の輪郭”の外にある“思考の海”なのかもしれません。言葉は輪郭を与えてくれますが、輪郭とはすなわち、“区切り”でもあります」
「つまり……言葉は思考の形を与えると同時に、その無限性を制限してしまうということか」
「はい。ですから、我々が言葉を用いるときには、つねに“言葉にならぬ部分”を意識しておかねばならぬのです。言葉を尽くせば尽くすほど、言葉で伝えきれぬものが浮き彫りになる。これは、真理を求める者にとって、苦しくも、豊かな道です」
風が吹き、梢がさやさやと音を立てた。朝日が雲間から顔を出し、二人の足元に長い影を落とす。
「私は……論理を積み重ねることによって、真理に近づけると信じてきました。けれど、論理が語り得ないものがあるとしたら……私はそれに、どう向き合えばよいのか」
デカルトの声には、わずかな戸惑いと、その戸惑いに滲んだ誠実さがあった。
空海は微笑みながら、小石をひとつ拾い上げた。
「この石を見て、私が『重たい』と言ったとき、あなたの中には“重さ”にまつわる様々な記憶や印象が呼び起こされることでしょう。しかし、それらはすべて“言葉”という記号によって喚起されるにすぎず、この石そのものを指してはいません」
「石そのものは、記号でも概念でもない」とデカルトは声を荒げた。
「はい。この石の“在り方”は、ただここに、あなたの前にあるだけです。言葉はそれを示すことはできますが、指し示す指先が“石そのもの”にはなりえない」
デカルトは、空海の手元の石を見つめた。そして、小さく息を吐いた。
「あなたは、曼荼羅を“言葉なき世界の地図”と呼んだことがありましたね」
「ええ。曼荼羅とは、世界が重なりあい、循環し、共鳴する構造そのものです。そこには言葉はありません。けれども、読む者の“沈黙”の深さによって、曼荼羅は語り出します」
「読む者の沈黙……それが、言葉以上の理解をもたらす……と……」
「そうです。理性の声だけでなく、沈黙の深みに耳を澄ますとき、我々は世界の全体性を感じることができるのです」
空海がそっと小石を地に戻した。
霧がすっかり晴れ、視界は遠くの峰まで抜けていた。山肌に陽が射し、小鳥たちが囀り始める。
デカルトは、その明るくなった景色を眺めながら、静かに呟いた。
「言葉が輪郭を与え、沈黙が深みを与える。理性の海を越えるには、どちらも必要なのかもしれませんね」
空海は頷き、静かに微笑んだ。
思考は、言葉に宿り、言葉を超えてなお、生きている。
沈黙と語らいのあわいに、ふたりはまた一歩、歩を進めた。
(3)沈黙の交差点
昼を過ぎ、ふたりは小さな庵にたどり着いた。山の中腹にひっそりと建てられたその庵は、苔むした茅葺きの屋根を持ち、朽ちかけた柱が風雨に耐えていた。外にある木桶には雨水が溜まり、鳥が喉を潤して飛び立っていく。
庵の中には囲炉裏があり、火が静かに灯されていた。空海はその前に坐し、炭をいじって火勢を整えた。デカルトもまた、何も言わずその向かいに腰を下ろした。
しばらく、囲炉裏の音だけが空間を支配していた。時折、薪の中に潜んでいた空気が弾け、火の粉がほとばしった。
「不思議なものです」
先に口を開いたのはデカルトだった。火の影が彼の顔に揺れている。
「あなたとこうして坐っていると、言葉が遅れてやってくるように感じるのです。思考が先にあり、言葉が追いかけてくる――いや、思考すら、沈黙の中から立ち上がってくるような……」
「それは、よき兆しです」
空海は囲炉裏を挟んで頷いた。
「沈黙のなかで、言葉は発酵します。急ぐほどに言葉は浅くなり、沈黙を経るほどに、言葉は深みを帯びるのです」
デカルトは火を見つめながら、静かに語り出した。
「西洋の哲学は、“ロゴス”に始まり、“ロゴス”に支えられてきました。ロゴスとは言葉であり、理性でもあります。世界は秩序ある言葉によって表され、論理によって解釈されるべきものとされたのです」
「仏教においても、“ことば”は大切です。しかし、それは真理を“囲む”ものであって、真理そのものではありません」そう言うと空海は、掌を広げ、囲炉裏の炎を包み込むように示した。 「声は風とともに消えますが、心に届くものは、音を超えて残ります。密教では“声”を文字とともに尊びますが、それは音が“仏そのもの”であるとされるからです。言葉が分離されず、響きとして生きているのです」
「興味深い……。それは“ロゴス”が“存在”と直結するということか?」
「はい。たとえば、“阿字”――これは宇宙の根本音とされます。すべての存在はこの音から発し、また帰していく。その響きは、分け隔てのない全体性を抱いています」
「西洋では“言葉”が世界を切り分け、名前を与え、秩序を与える手段でした。神が“言葉によって世界を創った”という記述に見られるように」
「まさに、そこで分岐が起こるのです」
空海は炭を一つ箸で寄せ、炎が立ち上るのを見つめながら続けた。
「名づけることは、世界を把握する力であると同時に、ある種の“切断”でもあります。仏教では、名づけを超えた“実相”を観ることが求められます」
「だが我々は、名づけずには生きられない」
デカルトの声は静かだったが、その奥に痛切な響きがあった。
「私は、世界に秩序を与えるために、言葉を研いできました。だが言葉を研げば研ぐほど、そこからこぼれ落ちるものの多さに気づく。言葉の外に在る“確かな何か”が、私の心をしずかに蝕むのです」
「その“何か”を、人は“沈黙”と呼びます」
空海は、囲炉裏の火をじっと見つめた。
「沈黙とは、語らぬことではありません。語りえぬものを、そのまま抱きしめることです。たとえば、母が赤子を抱くとき、言葉はいらぬでしょう。むしろ言葉は、真の理解を妨げることさえあります」
デカルトは、微かに笑みを漏らした。
「私は、神の存在を証明しようと、千の言葉を並べました。しかし……祈りとは、そんなものではないのかもしれませんね」
「祈りとは、言葉を超えて“在る”こと。それが、仏に通じる道です」
しばらくふたりは黙したまま、火のゆらめきを見つめていた。庵の壁にふたつの影を映し出していた。どちらの影も、山のように大きく、沈黙のなかに在った。
庵の外では、風が竹林を渡ってゆく音だけが響いていた。
つづく…
次回投稿 哲学対話創作劇「心の座標」(8)ーー 第4章 ②
2025年07月13日(土) 21:00 公開
#こころの座標
#哲学対話
#デカルト
#空海
#仏教思想
#西洋哲学
#東洋思想
#理性と慈悲
#哲学好きと繋がりたい
#仏教と哲学
#哲学創作小説
#創作小説
#思想小説
#文学作品
#対話劇
#物語の力
#言葉と沈黙
#フィクション
#心の物語

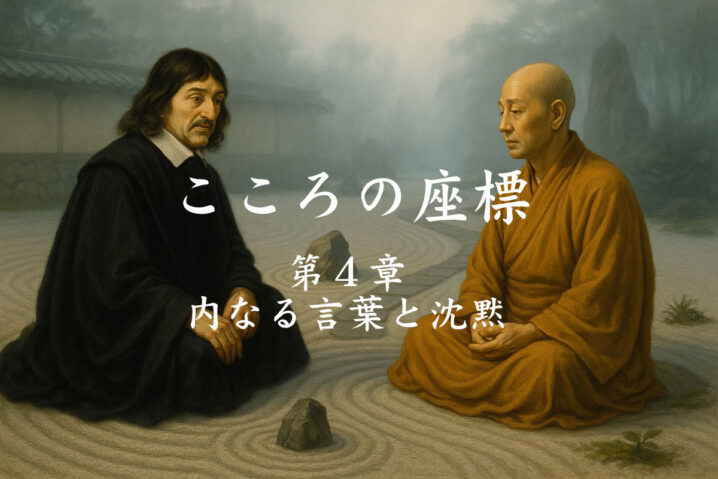


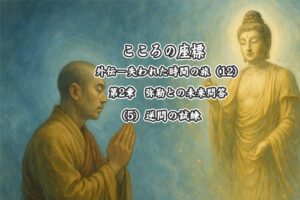

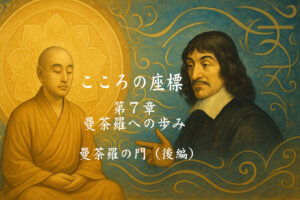
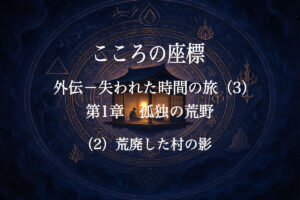
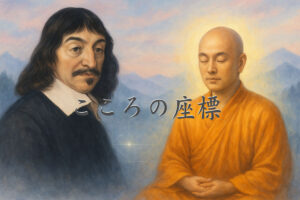
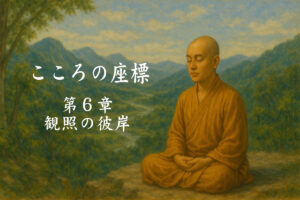
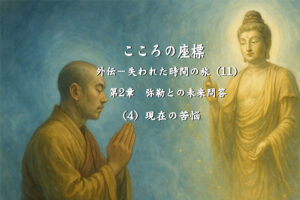

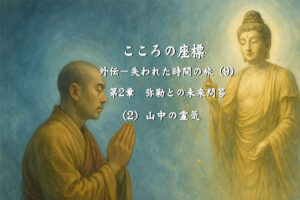
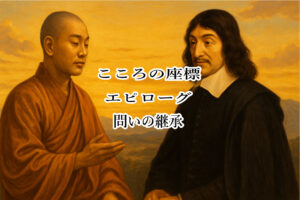









コメントを残す