(1)沈黙のあとに芽吹く問い
朝露が大地を潤し、草の匂いが空気に溶け込んでいた。
デカルトは霧を抜け、空海と別れたその先の道を一人り踏みしめるように歩いていた。
草原のなだらかな起伏を越え、まだ見ぬ地へと足を進めていた。
かつての彼ならば、あらゆる景色に論理を与え、法則性を見出そうとしただろう。
しかし今、彼の目に映る世界は、理性の対象ではなく共にある風景として現れていた。
朝日が差し込む。光が葉に反射し、万物が呼吸しているようだった。
歩くという行為が、彼にとって初めて沈黙の思考であると感じられた。
――歩くことで、私は世界に触れている。
――考えることと、生きることの間に橋が架かっていく。
その思いが、胸の奥にひっそりと根づいていく。
やがて、彼は小さな川辺にたどり着いた。水は浅く澄み、陽の光を受けてきらめいていた。
デカルトは腰を下ろし、手を伸ばしてその冷たさに触れた。
「理性は、流れる水のようであるべきか……?」と彼はそうつぶやいた。
かつては、理性は岩のように不動であることを理想とした。
しかし、今は違う。水は柔らかく形を持たず何処にでも流れ、しかし流れるからこそ大地を削り世界を形づくる力を持つ。
水は思考の比喩となった。
「私の理性は、固まりすぎていたのかもしれない」
その自覚は、新たな問いの入口となった。
川の音が静かに響く中、デカルトは自分の内にある理性の残響と向き合っていた。
流れる水に手を浸しながら、彼は思う。
理性は確かに道具であり、灯であり、盾であり、刃であった。
だが同時に、それは隔てるものにもなっていた。
「思考が、私を世界から引き離していたのか……」
自問するそのときだった。
対岸から、誰かが近づいてくる気配を感じた。
若い男だった。まだ二十代の半ばだろうか。
黒い外套をまとい、眉間に深い皺を寄せ何かに苛立ち、そして怯えているようにも見えた。
青年は、水辺の向こうからデカルトを見つけ立ち止まった。
しばらく沈黙があった。だがその空気は、敵意ではなく戸惑いによるものだった。
「……あなたは、このあたりの人間か?」
青年が口を開いた。
「旅の途中です」とデカルトは答えた。
「旅……何のために?」
その問いは、やや棘 とげを帯びていた。
「私自身を……知るために……」
デカルトの言葉に、青年は鼻で笑った。
「自己を知る? そんなもの、知って何になる。世界は理解できる構造ではない。
論理も秩序も、結局は崩れていく。私は、それを証明してしまった……!」
青年の眼には、理性を追い求め、そして理性に裏切られた者の光が宿っていた。
それは、かつての自分――過去のデカルトそのもののようでもあった。
「君は、なにを探していたのかね?」
「真理だ。数学のような、絶対的な真理。誰もが納得せざるを得ない唯一の答えだ。
だが……見つからなかった。いや、見つかったと思った瞬間、それはすぐに崩れ去った。
言葉の不確かさ、感覚のあいまいさ、そして――何より自分の思考すら疑わしい」
彼はしゃがみこみ、川の水を両手ですくい、顔を洗った。
「私は、どこまで信じればいい? 何を基準に確かさを決めればいい?」
デカルトは静かに彼の隣へ歩み寄った。
かつて、自分も同じ問いを抱えた。
そして、それを解決するために、『我思う、ゆえに我あり』へと至った。
しかし――
「君の問いは正しい。世界を知りたいという欲望、それ自体に間違いはない。
だが、君が苦しんでいるのは、確かさを完全性と取り違えているからではないか?」
青年は顔を上げた。
「完全性……?」
「完全な真理、誤りなき体系。それを求めるあまり、今ある不完全さを否定している。
だが、理性とは、必ずしも完璧であることではなく、問い続けることではないか?」
青年の表情が変わった。
「問い続ける……?」
「私も、すべてを疑った。そして、残ったものが『我思う、ゆえに我あり』だった。
だが、いま思う。あれは出発点にすぎなかったのだと。理性は閉じた円環ではなく、世界に触れながら変容する関係なのだと」
デカルトの言葉は、青年に向けてだけでなく自らにも向けられていた。
それは、思考の反復ではなく沈黙を経た言葉だった。
「君は、まだ若い。崩れた体系に絶望するのではなく、その崩れた場所から新しい問いを立ててみてほしい。
問いこそが、理性の命だ」
青年はしばらく沈黙していた。川のせせらぎが、静かに流れる。
やがて、青年は立ち上がり、デカルトに向かって深く頭を下げた。
「……ありがとう。私は、もう一度、問いから始めてみる」
デカルトは微笑み、彼の肩に手を置いた。
「それが、君の歩み出す理性だ」
(2)理性の再出発
青年が去ったあと、デカルトは川辺に腰を下ろし、しばらくその余韻に浸っていた。
言葉を交わすことで何かを変えることができる。
かつての彼なら、その感覚を心理的作用や意識の影響力といった形で捉えていたに違いない。
だが……今は違った。
人と人とのあいだに起きる理解の気配そのものが、理性の深層に触れるものだと直感していた。
「問い続けること――それが理性の本質なのかもしれない」
そう呟いた自分の声が、川のせせらぎに溶けていく。
以前の彼にとって理性とは、誤謬 ごしんなき構造体を築くための基礎だった。
ひとつひとつ疑い、壊し、最後に残る『思考する自我』だけを拠り所とした。
しかし、その硬質な哲学は、青年のような人々にとって孤独な塔にもなっていたのではないか。
そんな懸念が心をかすめる。
空海の沈黙。青年の問い。そして、いま自分が歩むこの旅路。
理性とは、問いを繰り返しながら世界に寄り添う動きそのものである。
それは思考の中だけで完結するものではない。むしろ、世界に向かって開かれ、感受し、揺れ、再び立ち上がるための力だ。
デカルトは、川に小石をひとつ投げ入れた。波紋が静かに広がり、水面に円を描いた。
「思考も、こうして波紋のように広がっていくのかもしれない……」
そのとき、彼の中でひとつの確信が芽生えた。自分の哲学は終わったのではない。
それは、書かれたことで閉じられるのではなく、語られ、あるいは沈黙に支えられ、生き続けるものであるべきなのだと。
彼は立ち上がった。歩き始めた足は、前よりも軽く、しかも芯が確りと通っていた。
(3)理性の器
山道は徐々に険しさを増していた。足元の土は乾いており、踏みしめるたびに小石が転がる。
だが、デカルトの足取りは揺るがなかった。青年との対話を経て、彼の中には静かな確信が芽吹いていた。
――私の理性は、いまだ終わっていない。
振り返れば、あらゆる体系を築き、その堅牢さに誇りすら持っていた。
しかし、その哲学は、ある一点で停止していた。疑い尽くすという構造の中で今、彼の心はかつてないほど動いていた。
思考はもはや閉じた円環ではなく、『世界との交響』となりつつあった。
風の音、土の匂い、雲のかたち、沈黙の奥にある気配それら全てが、彼の理性とともに歩んでいるように感じられた。
やがて、山の中腹にたどり着いた。そこには岩の窪みがあり、小さな祠ほこら が置かれていた。
風で揺れる木々の音が、さながら古 いにしえの調べのように響いていた。
デカルトはその場に座し、再び静かに瞑目した。
その時だった。
「器とは、空であるからこそ、満たされるのです」
耳に届いたその声は、風が運んだ幻だったのか、空海の残響だったのか。
だが確かに、彼の胸の奥に届いた。
器……。
彼は、かつて理性を構造として捉えていた。
だが空海の言葉は、理性を「器」として捉えるよう促していた。
器とは、何かを受け入れるための空間だ。理性が空であればこそ、世界のあらゆる声を迎え入れることができる。
空であることは、不完全さではない。むしろ、無限に開かれているということだ。
「理性の完成とは、すべてを知ることではなく、全てに耳を傾ける用意があるということなのかもしれない」
その瞬間、彼の内にあった焦燥は、すっと音もなく消えていた。
変わらぬ問いを抱えたままでも、歩んでいけるという確信が生まれていた。
祠の前にして風がひとすじ、彼の頬をなでた。
まるで、空海がそっと微笑みかけたような感覚だった。
つづく…
次回投稿 哲学対話創作劇『こころの座標』
第3章 身と心との分水嶺 (1)(2)
2025年07月05日(土) 21:00 公開予定
#こころの座標
#哲学対話
#デカルト
#空海
#仏教思想
#西洋哲学
#東洋思想
#理性と慈悲
#哲学好きと繋がりたい
#仏教と哲学
#哲学創作小説
#創作小説
#思想小説
#文学作品
#対話劇
#物語の力
#言葉と沈黙
#フィクション
#心の物語

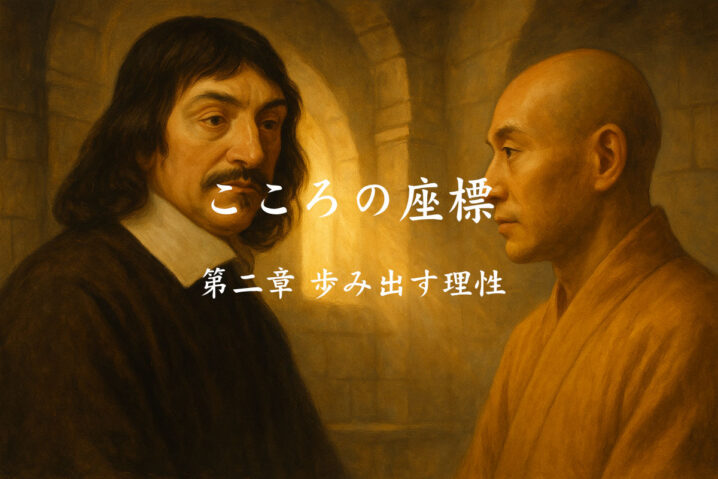


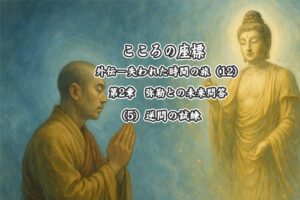
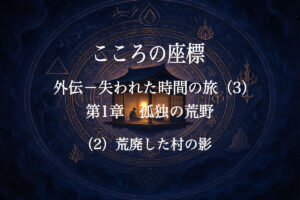

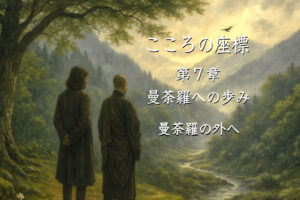
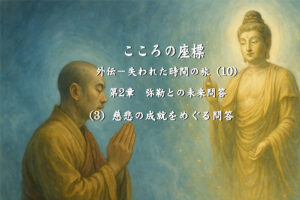
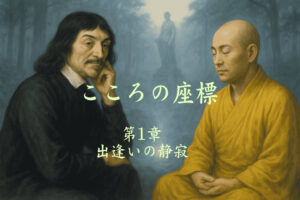
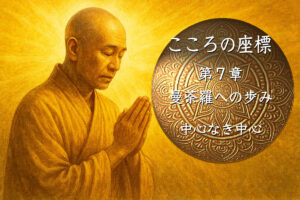

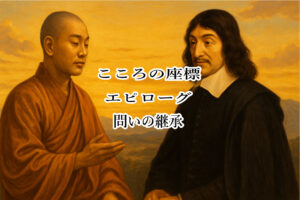










コメントを残す