読み終えるまで約12分
(1)地平を越えて
山道を抜けた瞬間、風の調子が変わった。谷から吹き上がる冷気は、刃のように肌を刺すのではなく、少し湿り気を帯びて、肺の奥を洗うように澄んでいる。空は薄い雲をまとって鈍く光り、東の端だけが白く起き上がろうとしていた。
眼下の川は、銀の紐のように蛇行している。川面に貼りついた薄氷はところどころ割れて、流れの速い筋だけが黒々と露わになっていた。
川沿いに並ぶ畑は、枯れた茎や支柱の影が斜めに伸び、ところどころに置かれた藁束が、冬の色の中でやわらかい黄を保っている。屋根の上では白煙がゆっくりと立ちのぼり、鶏の短い鳴き声が、間を置いて二度、三度と響いた。
デカルトは立ち止まり、手袋を外して掌をひらいた。冷気が指の間を抜ける。そのわずかな空隙に、彼は曼荼羅の細い線を思い出していた。
線は線でありながら、色にも、香にも、音にも開いていた──堂内で味わったあの“多声の平面”が、いま外界の風景と重なって見える。
「空海……」
彼は白い息とともに声を出した。
「私は、曼荼羅の中で見た秩序を、ここにも見えています。
川の蛇行、畑の列、煙の立ちのぼり、鳴き声の間……それらが互いに支え合って、一つの網をつくっている。
図を離れても、網は解けない」
空海は少しだけ顎を上げ、谷全体をひと撫でするように視線を運んだ。
衣の袖口からのぞく手は、ゆっくりと胸の前に集められ、合わされ、また解かれる。
「曼荼羅は絵ではなく、働きです」
声は低いが、冬の空に引っかかることなくまっすぐ届く。
「内にあっては形としてあなたを包み、外にあっては縁としてあなたの歩みに絡みます。
あなたが“基盤”と呼んできたものが、いまは“呼吸”として胸に在る。
呼吸は固定されない。ですが、呼吸なくして何ものも立ち行かない」
デカルトは指先を再び握り、手袋をはめた。
「呼吸を基盤と呼ぶなら、理性は何を担うのでしょう。
私は理性を、世界から距離を取るための道具だと信じてきた。
切り分け、定義し、疑い、たどり着いた確かさだけを拠り所にする……。
けれどいま、理性さえも、この網の中の一節に過ぎないように感じます」
「理性は網を切る刃である前に、網の震えを聴く耳でもあるのです」
空海は一歩、雪を踏んだ。雪は軽くきしみ、すぐに沈黙へ戻る。
「あなたは理性を研ぎ澄ました。研ぎ澄まされたものは、傷つけもするが、微細な震えを捉えることもできる。
曼荼羅の内では“音と沈黙”の往還を学びましたね。
外でも同じです。理性は沈黙に耳を澄ます術へと、かたちを変えうるのです」
そのとき、尾根道の下方で、牛を引く男が見えた。肩に古い鋤を担ぎ、ゆっくりと歩いている。牛が鼻を鳴らすたびに白い湯気が立ち、綱がかすかに震える。
少し遅れて、小さな子が二人、転ばぬよう足元を確かめながらついていった。
デカルトは、その歩の遅さに気づき、ふと自分の歩幅を思い出す。曼荼羅の前で空海に言われた言葉──。
「橋の中央には正誤の札は要らない。必要なのは、渡る歩幅を保つこと」
彼は胸の内で、歩幅という目盛りを調整する。早すぎず、遅すぎず、世界が進んでいく速さに歩みを合わせる。
「世界の座標……」
彼は呟き、谷に視線を渡す。
「それは、個としての私と、全体としての世界が交差する印なのですね。
マンデルブロ集合のように、どの縮尺にも同じ縁があらわれる──いや、比喩に頼るより、今はただ〈交差〉として受け取りたい」
空海は微笑を含む。
「座標は、点であり、場でもあります。思考の点に印をつけるだけでは、世界はほどけない。印のまわりを取り巻く“場”の気配ごと、座標は立ち上がる。あなたがいま感じている冷たさ、鼻腔を通る匂い、遠い鍬の音、そして言葉にしがたい“間”──それらが合わさって、ひとつの座標を結びます」
黙した時間が少し流れる。風は尾根を越えるたび、音の高さをわずかに変える。谷の底からは、雪の上を滑る|橇《そり》の鈍いきしみが届いた。
デカルトは背負ってきた旅の重さを、ゆっくりと下ろすように深呼吸した。
理性の荒野で孤独に火を熾した夜。言葉を研ぎすぎて手を切った日。曼荼羅の前で、中心が分裂し、器の空が胸に降りてきた瞬間。音が沈黙へ還り、沈黙が音を生む循環。
どれもが、点ではなく、場だった。彼はようやく、その連続に頷く。
「空海、私はこれから、理性を砦としてではなく、羅針盤として携えたい」
言葉を選ぶように、彼は続ける。
「針は固定されず、しかし北に引かれる。針そのものを疑いながらも、針のふるえに世界の磁力を聴き取る──そんな使い方を」
「よい喩えです」
空海は、袖の中でそっと指を結ぶ。
「羅針盤の針は、外の磁に触れてはじめて働きます。内に閉じれば、針はただの金属です。理性も同じ。世界の磁に触れ続けること。恐れず、しかし呑みこまれず」
道の脇に、氷柱が並んでいた。垂れ下がった透明の刃は、一列に並びながら一本ごとに長さも太さも違っている。デカルトは一本を指先で軽く弾いた。澄んだ音が鳴って、次に、隣の氷柱が共鳴して微かに震えた。
「座標は、単独では鳴らないのですね」
「はい。隣の震えが震えを呼び、その連鎖が“場の音”をつくる。曼荼羅の縁起は、まさにその連鎖の地図です」
その言葉に背中を押されるように、デカルトの中で“座標”の輪郭が具体性を帯び始めた。
一つは、時間の座標。個の時間、共同体の時間、季節の時間、地層の時間。
もう一つは、関係の座標。自他、ものとこと、語と沈黙、中心と周縁。
そして三つめは、態度の座標。観察・参与・祈り。
それら三軸の交差点に、彼はいま立っている──そう、体感として理解した。
「空海……」
彼は雪面に杖先で小さな十字を描いてみせた。
「この交差は、固定された原点ではない。歩くたびに、呼吸のリズムに合わせて、原点のほうがこちらに寄ってくる。
……いや、原点が移動するのではない。私が原点の働きになっていくのだ」
「“原点の働き”」
空海はその言い回しを転がすように繰り返し、頷いた。
「原点は、場所ではなく、ふるまい。あなたが座るとき、そこが座の“元”になる。あなたが聴くとき、そこが聴きの“元”になる。
曼荼羅の中心が器であるように、座標の原点も器です。満ちては空き、空いては満ちる」
下り坂を少し進む。雪は浅く、踏み跡はすぐに整う。笹の葉が雪の重みで頭を垂れ、時折、葉先から水滴が落ちる。頬に一滴、冷たさが弾ける。
彼らが尾根の陰に差しかかると、風が弱まり、音の層が増えた。遠くの鍛冶場から、鉄を打つ硬い響きが一定の間隔で届く。近くの枝では、小鳥が雪を払う気配を立てた。はるか下では、子どもが笑う。
デカルトは立ち止まり、目を閉じる。音が、層ごとに遠近を持って並ぶ。その並びが、曼荼羅の円環のように感じられる。中心は自分の耳の内奥にもあり、同時に谷の底にも、山のむこうにも散らばっている。
「私は、中心を探す癖をまだ捨てきれていません」
目を開けずに、彼は正直に打ち明けた。
「けれど、いまは、中心が“散在する”という事実に、かつてのような恐れを抱いていない。散在は崩壊ではなく、同時多発の支え合いだ、と身体が言っています」
「恐れの減衰は、和解の兆しです」
空海は小石をひとつ拾い、雪の上に置いた。「たとえば、この小石。あなたが座標の働きになれば、小石の重さに意味が宿る。あなたが働きをやめれば、小石はただの石に戻る。世界の側とあなたの側、その共同作業が、座標の印を残すのです」
デカルトは膝をつき、小石に手を添えた。石は冷たく、しかし乾いている。掌に伝う微かなざらつきに、彼は“現実”を感じる。
その現実は、否定しうる仮像ではなく、関係の働きのうちに立ち現れる実在──。
彼はゆっくりと立ち上がり、谷をもう一度見下ろした。
「空海。私は、理性と言葉をなお大事にしたい。だが、言葉が届かない余白を、切り捨てずに抱えたい」
「言葉の隣に沈黙を置き、沈黙の隣に祈りを置く」
空海は、以前の言葉をもう一度ゆっくりと響かせた。
「その配列が、あなたの座標を強くする。配列は固定しない。時に言葉が前に出、時に沈黙が前に出る。入れ替わりながら、全体を保つ」
遠くで犬が吠え、すぐに止んだ。雲がほどけ、日差しが斜めに差し込む。斜面の雪面は、無数の微粒子の鏡となって、きらきらと反射する。
デカルトはその光のざわめきを、曼荼羅の金の箔と重ねた。箔は均一ではない。わずかな皺が、光の濃淡を生み、像に呼吸を与える。
世界の光も同じだ。均されず、凹凸を持ち、その凹凸が生の陰影をつくる。陰影があるから、眼差しに深さが宿る。
「空海、私はまた“地図”を描きたくなるでしょう」
彼は苦笑する。「座標の語を手に入れたがゆえに、すぐ地図化し、固定したくなる。それは私の|性《さが》です」
「それでよいのです」
空海は即座に言う。
「地図を描きなさい。ただし、旅の最中に。歩みを止めて、地図を“唯一の風景”にしないこと。歩いては描き、描いては捨て、捨ててはまた描く。曼荼羅が“生成する秩序”であるように、あなたの地図も生成するがよろしい」
そのやり取りののち、二人はしばし言葉を失った。言葉の不在が、不安ではなく、満ち足りた静けさとして在る。
やがてデカルトは、深く息を吐いて言った。
「私は、もう孤独を“切り札”にしないでしょう。孤独は必要な時にだけ、座標を見直すための静かな机としてひらく。普段は、世界の机で書く。人と物と出来事のざわめきの中で」
「それが、外へ出た者の姿です」
空海は尾根から少し外れ、雪の浅い場所に足を置いた。
「曼荼羅は、堂の壁にあっては学びの面であり、外の世界にあっては歩きの面です。あなたはすでに、面の裏と表を行き来できる」
谷底から、小さな鐘の音がした。老いた寺の朝の合図だろうか。鐘は空気を押し出し、すぐに広がる。耳が捉えるのは一撃だが、世界はその余韻をゆっくり持続させる。
デカルトはその持続に合わせて、一つの言葉を胸に刻んだ。
──座標は、呼吸である。
吸うとき、世界は内に満ち、吐くとき、世界は外に溢れる。
その往還が、私と世界の“交差”を絶えず新しくする。
「空海」
彼は振り返り、深く一礼した。
「ありがとう。あなたの言葉は、私の地図を燃やす火であり、また照らす灯でもあった」
空海は首を振る。
「私の言葉も、誰かの言葉の受け渡しです。あなたが受け取って、自らの呼吸で温め直した。それがすべてです」
二人は歩き始めた。尾根を降りる道は、ところどころで細くなり、岩が顔を出している。足裏に伝わる硬さが、現実の重みを保証する。
途中、小川を渡る丸太橋があった。凍りついていない中央だけが濡れ、陽に光る。デカルトは、一歩ごとに呼吸を合わせ、視線を足元と対岸とに交互に配る。
橋の中央で、ふと、彼は立ち止まった。
中央──正と負、此岸と彼岸、言葉と沈黙の、いっときの均衡点。
彼は短く、しかし確かに微笑んだ。
そして……渡った。
道は里へ向かって開けていく。畑の端で、老女が背を丸めて霜柱を踏み崩している。家々の前では、子どもが雪玉を転がし、犬がそれを追って吠える。パンを焼く匂いが風に乗ってきて、腹の底を優しく刺激する。
デカルトは、世界の匂いを嗅ぎわける鼻を、自分が持っていることに気づく。言葉の鼻ではなく、生活の鼻。曼荼羅の香ではなく、パンと土と焚き木の匂い。
それは、彼にとって新しい種類の喜びだった。
「空海、私は座標の“軸”を少し言葉にしておきたい」
歩きながら、彼は整えるように語る。
「時間──個の時間・季節の時間・共同体の時間・歴史の時間。
関係──自他・ものこと・語・沈黙・中心周縁。
態度──観察・参与・祈り。
この三つの軸を、状況に応じて回し、入れ替え、傾ける。それが世界に対する私の“姿勢の技術”になる」
「技は、身に落ちた時に完成します」
空海はやわらかく応じる。
「あなたはすでに、橋の上でそれをやっていた。足元、対岸、呼吸。視線と息と足の置き場所を入れ替え、傾け、保った。紙に描かれた図ではなく、歩きの図です」
村の入口に、古い道標が立っていた。風雪に磨かれた木の板に、かすれた文字で三つの地名が刻んである。どの方向も、誰かの暮らしへ続いている。
デカルトは、道標に手を触れ、木目の凹凸を確かめる。
「世界の座標は、地図の中心ではない。道標の足元だ」
彼は、自分に聞かせるように小さく言った。
「ここに立ち、そこへ向かう。その“ここ”が、息と視線と関係でできている限り、私は迷わない」
空海は、彼の横顔をしばらく見、それから視線を前に戻した。
道の先で、朝日が雲間から顔を出す。金色の刃ではない。白く柔らかい、冬の光だ。
光は、二人の影を長く延ばす。影と影が触れ、離れ、また触れる。
デカルトは、影の交差に目を留め、くすりと笑った。
──座標は、いまここで、たえず更新されている。
やがて、最初の家の前に着いた。戸口に掛けられた木札には、手書きの小さな字で「パン」とあり、下に本日の品書きが添えられている。焼き立ての円いパンが二つ、木の台に布をかけて休んでいた。
店の主が戸口に出て、軽く会釈をする。
「おはようございます」
デカルトも会釈を返す。言葉の意味は半ばしかわからない。しかし、彼は臆せずに微笑み、胸に手を当てた。
座標の“礼”は、語の一致に先立って、身振りの調律として働く。
パンの温かさが袋越しに手のひらへ移る。外へ出ると、世界の匂いが少し増している。
デカルトは、袋を両腕で軽く抱え、空海の方へ顔を向けた。
「行きましょう。歩きながら、食べましょう。歩きながら、描きましょう。描きながら、捨てましょう」
「ええ」
空海は微笑のまま、ただ一言で応えた。
彼らは、村を貫く細い道を西へと歩き出した。
足元で雪が軋み、どこかの家の戸が閉まる音がして、犬がもう一度だけ吠えた。
山の尾根に、残りの霧が薄くたなびいている。
尾根の向こう側には、まだ見ぬ谷があり、まだ見ぬ人の暮らしがある。
世界の座標は、そこにも置かれているだろう。
彼らがそこへ至るとき、また別の呼吸で、また別の配列で。
それを思うと、デカルトの胸は、不思議な静けさと小さな昂ぶりで満たされた。
パンをひとかけ|齧《かじ》る。外は薄く硬く、中は温かく柔らかい。歯が沈むと、ほんの少し甘い香りが鼻へ抜ける。
彼はふと、堂内の香の記憶と、このパンの香りを、同じ座標の軸上に置いてみる。
祈りと食事。沈黙と|咀嚼《そしゃく》。どちらも、世界と自分の交差が確かめられる行いだ。
彼は、笑った。
空は、先ほどよりも色を増し、薄い銀から淡い青へと移る。雲の切れ間から、微かな鳥の群れが南へと渡っていくのが見える。
その小さな影の列に、デカルトは自然に敬意を払う。
正確な隊列。だが、完璧ではない。羽ばたきは同期しているようで、微妙にずれる。
ずれは、乱れではない。生きているための余白だ。
彼らの歩みもまた、完全な並足ではない。
ときにデカルトが半歩先に出、空海がそれに合わせる。
ときに空海が斜面の浅いルートを選び、デカルトがその後を踏む。
歩幅が、呼吸が、微かにずれては重なり、重なってはずれる。
その合わせ目に、彼らの“いまの座標”が立つ。
村はずれの小さな橋を渡り終えたところで、デカルトは振り返った。
来た道が、一本の糸のように細く見える。
糸は、彼らが歩いたからこそ、そこに“見える”。
世界の座標は、用意された交点ではなく、歩いた痕跡が光って見える現象だ──。
彼は、胸の内でその言葉を一度だけ|反芻《はんすう》し、そっと手放した。
前方の道標に、新しい刻字が見える。
「港 →」「森 ←」「峠 ↑」
空海は、港の矢印を指さした。
「水の座へ。呼吸のもう一つの|相《すがた》を見に行きましょう」
「ええ」
デカルトは頷く。
水は、曼荼羅の“器”の原型だ。満ちては空き、形なくして万形を受ける。
港へ向かう路は、わずかに潮の匂いが混じっている。
彼らは、そこへ向かって歩き出した。
足元で雪がまたひとつ、やさしくきしんだ。
つづく…

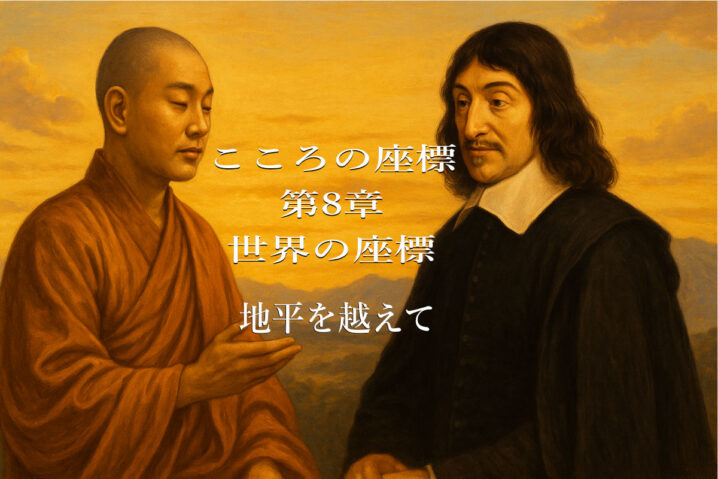

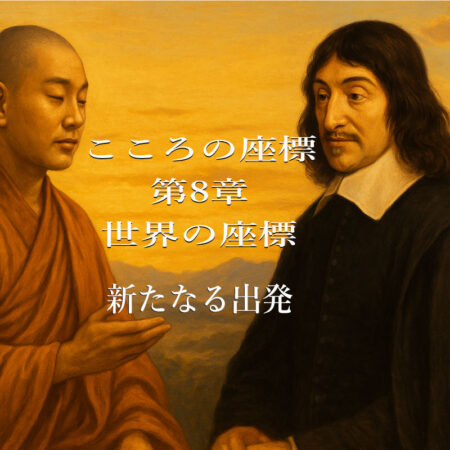

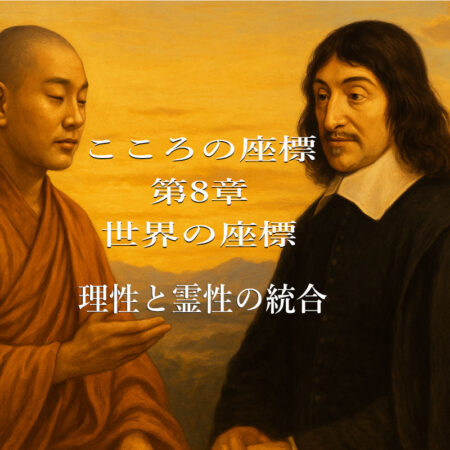
























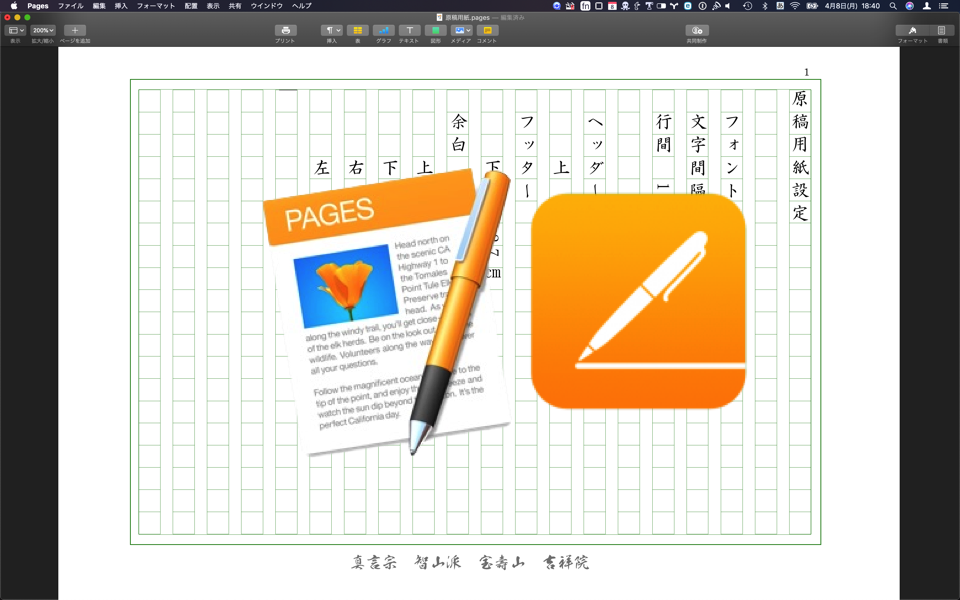

コメントを残す