読了時間 約5分
(3)自己と世界の鏡像
夜が明ける少し前、海辺の町はまだ眠っていた。
波の音が、眠る家々の屋根をやさしく撫でて通り過ぎる。
デカルトは宿の窓辺に立ち、ゆらめく灯の残り火を見つめていた。
海から吹く潮風が、微かに肌を冷やす。
外はまだ薄闇で、水平線と空の境界が曖昧だった。
だがその曖昧さが、彼の心には心地よかった。
夜のあいだに、彼の内で何かが静かに組み替えられていた。
言葉と沈黙が交わった昨日の対話の余韻が、波の音に混ざって残っている。
それは、理性の思索ではなく、胸の奥で“聴こえているもの”だった。
――思考の中心が、ゆっくりと移動している。
空海は早くに起き、海辺の岩の上で座していた。
衣の裾が潮に濡れ、白い布地が朝の光を吸い始めている。
彼の周りには、塩の香と風の唸りが渦を巻き、まるでその姿ごと自然に溶け込んでいるようだった。
「おはようございます」
デカルトが声をかけると、空海は静かに頷いた。
「おはようございます。……この海を見てください。
あなたには、どのように見えますか?」
デカルトは視線を海へ移した。
朝靄の向こうで、波が幾層にも重なりながら崩れ、また立ち上がる。
遠くの水平線は、まだ眠っている太陽の光を受けて、かすかに金色に揺れていた。
「世界が息をしているように見えます」
「ええ。あなたもまた、その息の一部です」
空海は立ち上がり、砂の上に足跡を残しながら歩き出した。
デカルトも続く。
波打ち際を歩く二人の足跡は、潮が寄せるたびに消され、また現れた。
「私たちの存在も、こうして世界に書かれ、消される。
けれど、消えることは無ではない。
海はあなたの形を覚えているのです」
空海の声は、風の中でもはっきりと届いた。
「覚えている……?」
「ええ。波が去るとき、砂の粒が少しだけ位置を変えます。
そのずれが、記憶です。
世界は、無数の小さな“ずれ”によって、あなたを映し続けている」
デカルトは足元の波紋を見つめた。
寄せる波に映る自分の姿が、形を変えながら現れては消える。
その像は、自分であるようでいて、そうでないもののようにも感じられた。
彼はふと、胸の奥で、これまで築いてきた「自己」という像がぐらりと揺らぐのを感じた。
「我思う、ゆえに我あり」。
その確信の輪郭が、波に呑まれ、ゆっくりと溶けていく。
「空海……もし、私という存在が、世界の鏡像にすぎないとしたら、私の思索の基礎はどうなるのです?
“思う私”は、“映る私”に過ぎないのでは?」
空海は微笑んだ。
「それでいいのです。映るものこそが、世界の光を受けて存在する。
あなたの思索もまた、世界の呼吸に映された“ひとつの影”です。
鏡が光を拒めば、像は生まれません。
あなたの理性は、鏡なのです」
デカルトは沈黙した。
彼の内で、理性という硬質な刃が、少しずつ溶け、柔らかな光の面に変わっていくのを感じた。
世界は、切り分けるべき対象ではなく、映し合う関係そのもの――。
そう気づいたとき、胸の中に、説明を要しない確信が広がった。
「鏡は、どこにあるのですか?」
「鏡は、あなたの目の奥にあります。
そして、世界のあらゆる場所にもあります。
あなたの“見る”という行為そのものが、鏡を作っているのです」
空海は、海面に手をかざした。
光が手のひらに反射し、彼の顔に微かな陰影をつくる。
「見ることは、映すこと。
映すことは、関わること。
あなたが世界を見た瞬間、世界もまた、あなたを見返しているのです。」
デカルトは、その言葉に息を呑んだ。
彼はこれまで、観察者として世界を“前に置いて”きた。
主観と客観。
主体と対象。
世界は、思考の対象として“他者”であると信じてきた。
しかし、今は違う。
世界は、鏡越しにこちらを見ている。
彼が“世界を知ろう”とする瞬間、世界もまた、“彼という現象”を生じさせているのだ。
潮が満ち始め、波が強くなった。
空海の袈裟の裾が大きく揺れ、海水がその裾を濡らす。
「見てください」
空海が指さす先に、群れをなすカモメがいた。
風に乗って一斉に舞い上がり、旋回して、また降りる。
その白い翼の群れが、まるで空の波のように上下していた。
「彼らは、自分の翼の影を、海に映して飛んでいる。
海は、空を映しながら、同時に彼らの影を受け止めている。
映すものと映されるものは、ひとつの呼吸のなかにあります」
デカルトはその光景を見つめ、胸の奥が熱くなるのを感じた。
――私は世界の観察者ではない。
私は、世界の“反映の一部”なのだ。
この気づきは、思考の勝利ではなかった。
むしろ、思考の“降伏”に似ていた。
だが、その降伏は敗北ではない。
思索が、ようやく自らの限界を愛せるようになった瞬間だった。
「空海……もし自己と世界が鏡像であるなら、善と悪、苦と楽、真と偽もまた、互いを映す像なのでは?」
「そうです」空海は頷いた。
「それらは対立ではなく、映り合う光と影。
影を嫌えば、光も歪みます。
だからこそ、私たちは“どちらの面にも宿る命”を見なければならない。
それが“縁起”の鏡です。」
デカルトの目に、波の一つが飛沫を上げて砕ける様が映った。
砕けた水粒が光を受け、無数の小さな虹となって舞う。
その瞬間、彼の中でひとつの像が完成した。
――世界は、自己の鏡。
自己は、世界の反映。
理性は、光を磨く鏡であり、霊性は、その鏡に宿る水面のゆらぎ。
どちらが先でも、どちらが上でもない。
「私は今ようやく、理性の“根”が、世界の中に伸びていることを感じます。
思考は孤独な行為ではなく、世界と共に呼吸することなのですね。」
空海は微笑んだ。
「あなたがその呼吸に気づいたとき、理性は世界の一部として開かれます。
それは“我思う”の先にある、“我在る、ゆえに世界あり”という地点です。」
その言葉に、デカルトは深く息を吸い込んだ。
潮の香りが肺の奥まで満ちる。
体が、思考よりも先に世界を感じ取る。
波音が心臓の鼓動と重なり、区別がなくなっていく。
自他の境界が、柔らかくほどけていく感覚。
空は白み、朝日が水平線の端から顔を出した。
光は海面を滑り、二人の頬に届く。
その光の中で、デカルトは自分の影が砂の上に伸びていくのを見た。
だがその影も、やがて波に消されていく。
――消える。
だが、確かにここにあった。
世界は、その消えゆく軌跡を覚えている。
空海が静かに言った。
「あなたが世界を見つめるとき、世界もまたあなたを見つめています。
鏡は、常に両側を映します。
そしてその真ん中に、無数の縁が光るのです。」
デカルトは目を閉じ、頬を撫でる風に微笑を返した。
理性は、もはや彼を孤立させる塔ではなかった。
理性は、世界の鏡に映る、一瞬の光。
それが彼の、新しい「存在の座標」だった。
つづく…

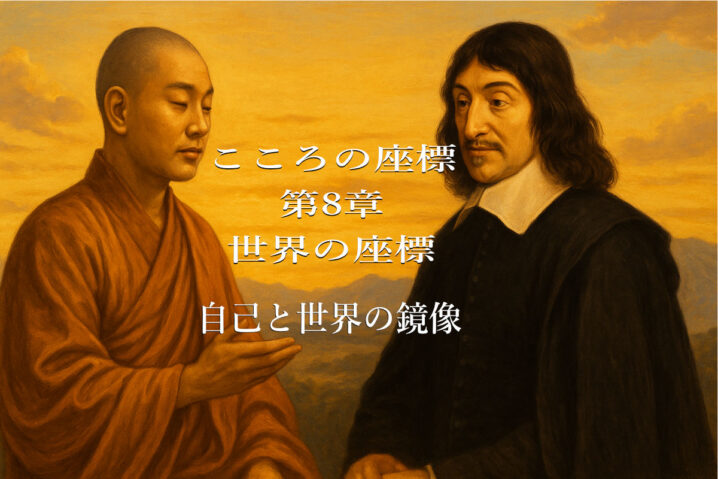

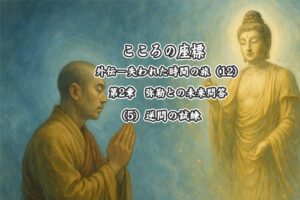
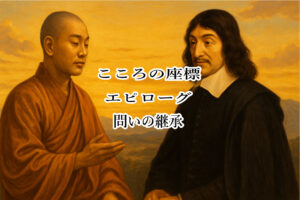
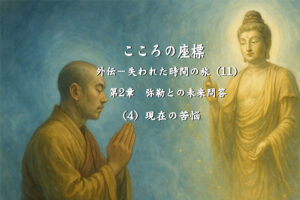
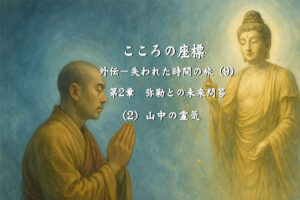
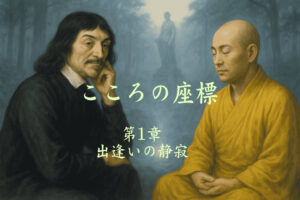
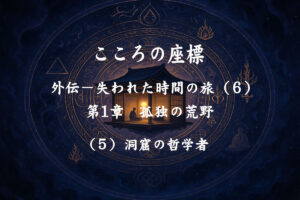
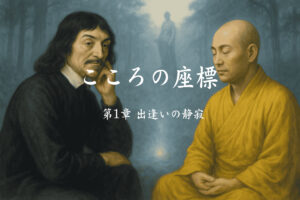
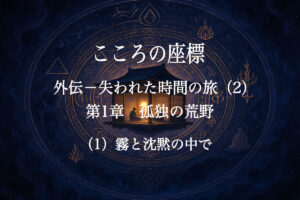
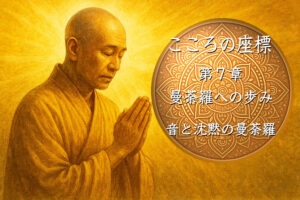
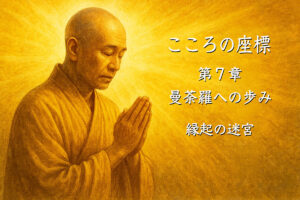
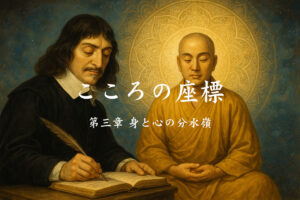





コメントを残す