📖読了時間 約3分〜5分
(6)光の兆し
洞窟の出口に立ったデカルトの目の前には、まだ夜の帳が世界を包んでいた。
空は深い群青に染まり、星々はその光を弱めながらも、なお冷たく瞬いていた。
頬をかすめる空気には湿り気があり、長い沈黙のなかで吸い込まれた闇の記憶が、まだ体から抜けきっていないようだった。
一歩。石から土へ、土から砂礫へと、足元の感触が変わっていく。靴底が触れるたび、大地はわずかに振動し、それが彼自身の存在を確かめるようでもあった。
だが、その音すらもすぐに夜の静寂に吸い込まれ、あとには沈黙だけが残った。
彼は歩く。足の裏で確かめるように、一歩ずつ、慎重に。
そして心の中では、洞窟で交わされた数々の言葉がまだ反芻されていた。
問い、対話、沈黙。自分が誰であり、何を求めていたのか――その根源に触れた余韻が、彼の内側にかすかに残っていた。
やがて東の空に、ほんのわずかな変化が訪れた。最初は気づかないほどの色の濃淡だったが、それは確実に夜の終わりを告げるものであった。
群青が薄れ、鉛のような灰色が空を横切り、次第に紫がその縁を滲ませていく。
そして橙色の光が、まるで地平線の奥から誰かがそっと灯した小さな火のように、やさしく、静かに広がっていった。
デカルトは足を止めた。呼吸を整え、静かにその光を見つめる。朝はまだ完全には来ていなかったが、確かに「兆し」があった。
闇を裂くように始まるものではなく、闇を抱きながら少しずつ広がる、そうした優しさに満ちた始まりが、今この瞬間にあった。
「――暗闇があったからこそ、この光を感じる。
――孤独があったからこそ、問いは生まれる。
……ならば私は、 の孤独を背負って歩むしかない」
その独白は、夜明けの空へと滲み、風に溶けた。返事はなかった。
だが、言葉を外へ解き放ったこと自体が、彼の心に静かな余白をもたらした。
それは無言の対話。誰もいない世界との、あるいは彼自身との応答なき呼びかけだった。
ふと、遠くに小さな灯が揺れているのが見えた。風に揺らぐ炎のような光が、いくつも列をなして、こちらに近づいてくる。やがて複数の人影が、松明を掲げて黙々と歩く姿となって現れた。
彼らの衣は粗末で、顔はほとんど見えなかった。だが、炎の明滅がその輪郭を赤く照らし、足音は乾いた大地に一定のリズムを刻んでいた。
彼らはデカルトの存在に気づくと、互いに顔を向けて頷き合い、言葉を交わさずに通り過ぎていった。
その一瞬の交差はあまりに静かだったが、なぜか、胸の奥にあたたかなものが宿った。
「私は一人である。だが、一人で歩いているのは私だけではない!」
その気づきは、孤独を消し去ったわけではなかった。だが、孤独の底にもう一つの層が生まれたような感覚があった。誰もが問いを抱え、答えなき道を歩んでいる。言葉にされずとも、その足音が、歩みそのものが語っていた。
空の色は刻一刻と変化し、霧は山裾からゆっくりと上がっていった。
鳥の声がどこからともなく聞こえ始め、風には青草と湿った土の匂いが混ざっていた。
夜に隠されていた生命の徴が、まるで合図でもあったかのように姿を現し始めた。
虫の羽音、水の流れ。見えないものたちの動きが、静かな地鳴りのように彼の周囲を包んでいく。
デカルトは胸に手を置いた。心臓の鼓動を感じながら、深く息を吸い込む。その肺の奥にまで入り込む空気には、過去を背負い、未来へ向かう存在としての〈私〉を、再び抱きしめるような、どこか懐かしい清冽さがあった。。
「問いこそが、私を歩ませる。
答えはなくとも、問いが尽きぬ限り……私は立ち止まらない」
その言葉はもはや独白ではなかった。
彼自身に向けた宣言であり、歩みの約束であった。
太陽の光が、ようやく荒野を照らし始めた。長い影が彼の背後に伸びる。
だがその影すら、もはや彼の歩みを遮るものではなかった。
前方には、新たな道が、霧の向こうからゆっくりと姿を現しつつあった。
どこへ続くかは分からない。だが確かに、その道は存在している。
まだ誰の足跡も刻まれていない、その白紙のような大地の上に。
デカルトは歩を進めながら、遠い未来に出会うはずの誰かの姿を、ふと心に描いた。
光に包まれた曼荼羅の門。その前に、静かに佇む一人の僧。その存在はまだ記憶の中にはない。だが、それは確かに「再会」の予兆だった。
そして、その火は、小さくとも確かに彼の心に灯っていた。
つづく…

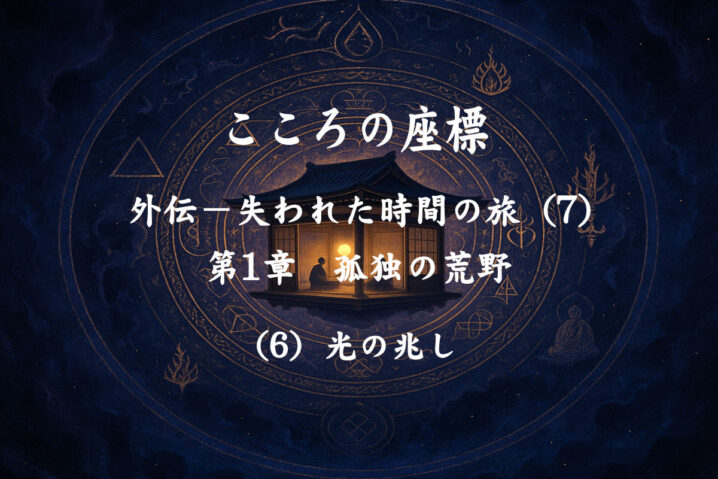
















コメントを残す