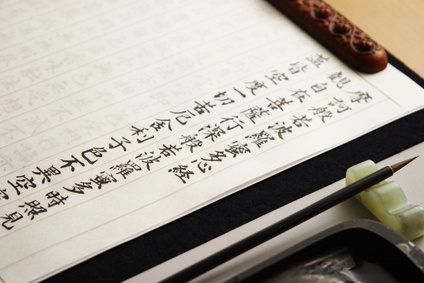【長編連載小説】 『こころの座標 外伝:失われた時間の旅』(16)第3章 戦場の影と幻影の師 血に染まる大地―②
戦場の中央から少し離れた場所には、奇妙な静けさがあった。
剣戟も怒号もすでに遠く、ここにあるのは、命がゆっくりと失われていく音だけだった。音と言っても、耳で捉えられるものではない。呼吸が擦れる感触、血が土に染み込む気配、身体の熱が冷えていく時間――そうしたものが、重なり合って空気を満たしていた。
デカルトは歩いていた。
第1節で見た死者たちの影は、まだ網膜の奥に焼き付いている。だが、ここでは死はすでに終点ではなかった。終わりきれない命が、低く、しかし確かに呻いている。